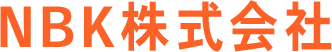タップ溶接とは?タック溶接との違いや強度、溶接記号、英語表記を解説
タップ溶接とは、溶接線を断続的に行う「断続すみ肉溶接」の一種です。
部材の接合において、必ずしも連続した溶接が必要ない場合に採用され、コスト削減や熱によるひずみの抑制を目的とします。
しばしば仮止めを目的とするタック溶接と混同されますが、タップ溶接は最終的な強度を担う本溶接であるという明確な違いがあります。
この記事では、タップ溶接の基本から、類似工法との違い、メリット、種類、図面記号、強度、そして英語表記までを解説します。
タップ溶接(断続すみ肉溶接)の基本的な概要
タップ溶接は、正式には「断続すみ肉溶接」と呼ばれ、溶接線を一定の間隔をあけて断続的に施工する溶接方法です。
長い距離の接合において、全ての区間を溶接する必要がない、あるいは過剰な品質となる場合に用いられます。
連続して溶接する全周溶接と比較して、溶接金属の使用量や作業時間を削減できるため、生産性の向上とコストダウンに貢献します。
また、母材への入熱量を抑えられることから、熱ひずみの発生を低減できるという大きな利点も持ち合わせています。
これらの特徴から、特に薄板の溶接や、高い寸法精度が求められる構造物の組み立てに適しています。
タップ溶接とタック溶接の目的・強度の違いを解説
タップ溶接とタック溶接は、どちらも断続的に短い距離を溶接する点で見た目が似ているため、混同されやすい工法です。
しかし、両者は溶接の目的と求められる強度が根本的に異なります。
タップ溶接は構造物が必要とする強度を確保するための「本溶接」であるのに対し、タック溶接は本溶接を行う前の位置決めを目的とした「仮止め溶接」です。
この違いを理解することは、設計や施工管理において極めて重要となります。
目的の違い:本溶接か仮止めか
タップ溶接は「断続すみ肉溶接」とも呼ばれ、断続的に溶接することで金属同士を接合する方法です。これは本溶接の一種ですが、強度があまり必要でない箇所や、熱による歪みを抑えたい場合などに用いられます。例えば、カバーなどの溶接に適しており、溶接にかかる手間やコストを削減できるという利点があります。しかし、高い強度や気密性が求められる箇所には不向きとされています。
一方、タック溶接は「仮付け溶接」とも呼ばれ、本溶接を行う前に部材同士を正しい位置に一時的に固定することが目的です。一般的に「点付け」と表現されることもあります。
タック溶接は、本溶接の熱や自重によって部材がずれたり動いたりするのを防ぐために行われます。本溶接が行われる際には、そのまま溶かし込まれるか、不要であれば除去されることもあります。
このように、タップ溶接が最終的な製品の一部となる本溶接(ただし、強度があまり要求されない場合)であるのに対し、タック溶接はあくまで組立工程における一時的な手段であるという点で、目的が明確に異なります。
強度の違い:求められる役割が異なる
目的が違うことから、タップ溶接とタック溶接では求められる強度も大きく異なります。
タップ溶接は本溶接として構造物の強度を分担するため、荷重に耐えうる十分な強度が求められ、そのための強度計算が事前に行われます。
溶接の長さ、ピッチ、脚長といった要素は、すべて必要な強度を満足するように設計で定められます。
対して、タック溶接に求められる強度は、本溶接が完了するまでの間、部材の位置を保持できる最低限のものです。
したがって、タック溶接に対して特別な強度計算が行われることは通常ありません。
役割が恒久的か一時的かによって、強度に対する考え方が根本的に違うのです。
溶接部品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
タップ溶接とスポット溶接は何が違うのか
タップ溶接とスポット溶接は、点状または線状に断続的に接合するという点で共通しますが、その原理と用途は全く異なります。
タップ溶接は、アーク放電の熱を利用して溶加材を溶かし、部材を接合するアーク溶接の一種です。
一方、スポット溶接は、重ね合わせた母材を電極で挟み込み、大電流を流すことで発生する抵抗熱を利用して圧接する抵抗溶接の一種です。
主に薄板の点接合に用いられ、自動車のボディなどで多用されます。
また、関連する工法として、気密性を目的とするシール溶接や、ナットなどを部材に取り付けるナット溶接も点溶接(スポット溶接)の応用例として挙げられます。
タップ溶接を採用する2つの大きなメリット
タップ溶接を連続溶接の代わりに採用することには、主に二つの大きなメリットが存在します。
一つは、溶接長が短くなることによる作業時間の短縮とコスト削減です。
もう一つは、母材への総入熱量を低減できることによる熱ひずみの抑制効果です。
これらのメリットは、特に長い部材の接合や薄板構造物の製作において大きな効果を発揮します。
溶接箇所を交互に配置する千鳥断続すみ肉溶接などの手法を用いることで、ひずみ抑制効果をさらに高めることも可能です。
溶接作業の時間を短縮して効率化できる
タップ溶接は、連続溶接に比べて溶接を行う部分の総延長が短くなるため、溶接作業にかかる時間を大幅に短縮できます。
溶接時間の短縮は、溶接棒やシールドガスといった消耗品の使用量削減にも直結し、結果として製造コストの低減につながります。
また、図面には溶接記号を用いて、溶接の長さやピッチが明確に指示されます。
この図面指示に基づき作業を行うことで、作業者のスキルによるばらつきを抑え、安定した品質を確保しながら効率的に作業を進めることが可能です。
明確な記号による指示は、作業の標準化を促進し、生産性向上に大きく貢献します。
母材への入熱を抑え熱ひずみを最小限にする
溶接は局部的に高温の熱を加えるため、母材の膨張と収縮によって熱ひずみが発生します。
タップ溶接は、溶接箇所と非溶接箇所が交互に存在するため、母材全体に加わる総入熱量を低減させることが可能です。
この特性により、特に熱による変形が生じやすい薄板や長尺の部材において、反りやねじれといった熱ひずみを最小限に抑えることができます。
適切な強度を確保しつつひずみを抑制するためには、設計段階で強度計算に基づいた溶接長さとピッチを決定することが重要です。
脚長や溶接長さは、強度確保の目安となると同時に、入熱量をコントロールする重要なパラメータとなります。
タップ溶接の代表的な2つの種類
タップ溶接、すなわち断続すみ肉溶接は、溶接ビードの配置方法によって主に二つの種類に分類されます。
一つは、継手の両側に溶接ビードを平行に向かい合わせて配置する「並列断続すみ肉溶接」です。
もう一つは、両側のビードを互い違いになるように配置する「千鳥断続すみ肉溶接」です。
どちらを選択するかは、求められる強度、部材の形状、そして熱ひずみをどの程度抑制したいかといった設計上の要求によって決定されます。
並列断続すみ肉溶接:溶接箇所が平行に並ぶ手法
並列断続すみ肉溶接は、T継手のような接合部において、ウェブの両側に溶接箇所が向かい合うように平行に配置される手法です。溶接箇所が左右対称になるため、溶接による収縮がバランスよく作用し、角変形などを抑制しやすいという特徴があります。図面での指示や施工管理が比較的容易であるため、広く一般的に用いられています。英語での表記は「chain intermittent fillet welds」または「parallel intermittent fillet weld」です。 強度部材の接合において、ひずみよりも製作のしやすさを優先する場合などに適しています。
千鳥断続すみ肉溶接:溶接箇所が交互に並ぶ手法
千鳥断続すみ肉溶接は、接合部の両側で溶接箇所が交互に、互い違いになるように配置される手法です。
並列配置と比較して、同じ溶接量でも熱がより分散されやすいため、母材の熱ひずみをさらに効果的に抑制できるという大きなメリットがあります。
この特性から、特に薄板の溶接や、高い寸法精度が求められる製品に適しています。
ただし、全周溶接とは異なり、断続的に溶接するため気密性や水密性は確保できません。
英語では「Staggered Intermittent Fillet Weld」と表記され、”Staggered”が「互い違いの」という意味を表します。
図面で使われるタップ溶接の溶接記号の見方
タップ溶接の施工内容は、図面上にJIS規格で定められた溶接記号を用いて正確に指示されます。
設計者が意図した強度と品質を確保するためには、施工者がこの記号を正しく読み解く能力が不可欠です。
記号は、すみ肉溶接を示す三角形の基本記号に、脚長、溶接長さ、ピッチ(溶接間隔)の寸法情報を組み合わせて構成されます。
特に、並列配置か千鳥配置かによって記号の示し方が異なるため、その違いを正確に理解しておく必要があります。
並列断続すみ肉溶接の記号と寸法の記載例
並列断続すみ肉溶接は、基線の片側または両側にすみ肉溶接の記号(直角三角形)を配置して示します。
記号の横には、寸法が「脚長溶接長さ-ピッチ」の順で記載されます。
例えば、「650-100」という記載があれば、それは「脚長6mm、溶接長さ50mm、ピッチ100mm(溶接部の始点から次の溶接部の始点までの距離)」で溶接することを意味します。
基線の上下両側に同じ記号と寸法が記載されている場合、または片側に記載して対称記号が添えられている場合は、部材の両側に同じ仕様の溶接を平行に施工することを示しています。
千鳥断続すみ肉溶接の記号と寸法の記載例
千鳥断続すみ肉溶接を示す場合、溶接記号の配置が特徴的です。
基線を挟んで、上側と下側のすみ肉溶接記号(直角三角形)を、互い違いになるように左右にずらして記載します。
この記号のずれが、千鳥配置であることを明確に示しています。
寸法表記は並列の場合と同様で、それぞれの記号の横に「脚長溶接長さ-ピッチ」の順で記載されます。
例えば、基線の上側に「650-100」、下側にもずらして「650-100」とあれば、両側で仕様は同じですが、その位置が交互になっていることを指示しています。
この記号の違いを正確に読み取ることが、意図通りの施工につながります。
タップ溶接の強度を確保するためのピッチと長さの決め方
タップ溶接は最終的な強度を担う本溶接であるため、溶接部の長さとピッチは構造物が受ける荷重に対して十分な強度を確保できるように慎重に決定されなければなりません。
これらの寸法は単なる経験則ではなく母材の板厚、材質、継手形式、そして静的な荷重か動的な荷重かといった使用条件を考慮した強度計算に基づいて算出されます。
一般的に必要な強度が高いほど溶接長さを長く、ピッチを短く設定します。
ただし溶接長を増やすことは入熱量の増加につながり熱ひずみの原因となるため、強度確保とひずみ抑制のバランスを考慮した最適な設計が求められます。
タップ溶接を施工する際の3つの注意点
タップ溶接は作業効率やひずみ抑制に優れる一方、その断続的な特性から施工時に特有の注意点がいくつか存在します。
短い溶接を繰り返すため、溶接の始点と終点における欠陥の発生リスクが高まります。
また、非溶接部が存在することから、応力集中への配慮も必要です。
さらに、強度を担保する上で、図面で指示されたビードの長さやピッチを正確に守ることが大前提となります。
これらの点を遵守することで、タップ溶接のメリットを最大限に活かし、信頼性の高い構造物を作ることができます。
溶接の始点と終点でクレーターなどの欠陥が起きないようにする
タップ溶接は、短い溶接を繰り返すため、連続溶接に比べて溶接の始点と終点の数が非常に多くなります。
溶接アークを開始する始点では、十分な熱が与えられず溶け込み不足になりやすく、アークを停止する終点では、溶融池が急激に凝固することでクレーターや、そこを起点とする割れが発生しやすくなります。
これらの欠陥は著しい強度低下の原因となるため、始点での予熱や、終点での適切なクレーター処理を確実に行うことが、品質確保のために極めて重要です。
端部や角など応力が集中する箇所の溶け込みを確保する
タップ溶接では、溶接されている部分とされていない部分が交互に存在するため、溶接ビードの端部に応力が集中しやすい性質があります。
特に、部材の端部や角の部分に溶接ビードの端が位置する場合、応力集中が亀裂の起点となる可能性があります。
そのため、設計段階から応力が集中しやすい箇所を避けて溶接位置を計画したり、重要な箇所では連続溶接に切り替えたりする配慮が求められます。
施工においては、指示された溶接長さの端から端まで、均一で十分な溶け込みが得られるように管理することが重要です。
定められたビード長とピッチ間隔を遵守する
タップ溶接の強度は、図面に指示されたビード長(溶接長さ)とピッチ間隔によって担保されています。
これらの寸法は、構造計算に基づいて決定されたものであり、施工時に正確に遵守されなければなりません。
もし、指示されたビード長より短く施工したり、ピッチ間隔を広く取ってしまったりすると、溶接部の断面積が不足し、設計で想定した強度を得られなくなります。
逆に、ビード長を必要以上に長くすると、熱ひずみの増大やコストアップにつながるため、これも避けるべきです。
定められた寸法通りに施工することが、品質と性能を保証する上での基本となります。
タップ溶接の英語での呼び方
タップ溶接を英語で表現する場合、一般的には「IntermittentFilletWeld」という用語が使われます。
「Intermittent」が「断続的な、時々とぎれる」を意味し、断続すみ肉溶接を指します。
さらに、その種類によって詳細な呼び方が異なります。
溶接箇所が平行に並ぶ並列断続すみ肉溶接は「ChainIntermittentFilletWeld」と呼びます。
「Chain」は鎖を意味し、その見た目から名付けられています。
一方、溶接箇所が互い違いに並ぶ千鳥断続すみ肉溶接は「StaggeredIntermittentFilletWeld」と表現されます。
「Staggered」は「互い違いの、ジグザグの」という意味を持ちます。
国際的な図面や仕様書を扱う際には、これらの英語表記の知識が役立ちます。
まとめ
タップ溶接、すなわち断続すみ肉溶接は、溶接線を一定間隔で断続的に行うことで、コスト削減と熱ひずみ抑制を実現する効率的な工法です。
最終的な強度を担う本溶接であり、仮止めを目的とするタック溶接とは明確に区別されます。
配置方法には、溶接部が平行に並ぶ「並列」と、互い違いに並ぶ「千鳥」の2種類があり、図面記号によって使い分けられます。
この工法のメリットを最大限に活かすためには、施工時に溶接の始点・終点での欠陥を防ぎ、応力集中に配慮するとともに、図面で指示された溶接長さとピッチを厳守することが重要です。
溶接部品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら