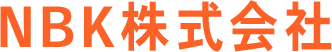アルミ溶接についてのコツを紹介
アルミを溶接したいと考えたとき、その方法やコツについて知ることは成功への第一歩です。
アルミニウムは鉄やステンレスとは異なる特性を持つため、特有の難しさがありますが、正しい知識と手順を理解すれば、個人でも美しい仕上がりを実現することは不可能ではありません。
この記事では、アルミ溶接とは何かという基本から、プロが実践する具体的な方法や失敗しないためのコツまでを網羅的に解説し、アルミを溶接する上での疑問や悩みを解決します。
なぜアルミ溶接はプロでも難しいと言われるのか?4つの理由を解説
アルミニウムという材質が持つ独特の性質は、溶接作業を難しいものにしています。
鉄とは異なる特徴を正確に理解しなければ、高品質な溶接は実現できません。
この材質特有の化学的・物理的な性質が、溶接時に様々な課題を生じさせるのです。
ここでは、アルミ溶接がプロにとっても技術を要するとされる主な4つの理由を、その特徴や性質と関連付けながら具体的に解説していきます。
理由①:頑固な酸化皮膜が溶接を妨げる
アルミニウムの表面は、空気中の酸素と反応して自然に形成される、非常に硬く融点の高い酸化皮膜で覆われています。
この皮膜は素材自体を保護する役割を果たしますが、溶接時には大きな障害となります。
アルマイト処理された製品も同様に強力な酸化皮膜を持っています。
この皮膜の融点は約2000℃と、アルミ母材の融点(約660℃)よりもはるかに高いため、皮膜が溶ける前に母材が溶け落ちてしまう事態を招きます。
そのため、溶接を始める前には、ワイヤーブラシや薬品を用いてこの頑固な酸化皮膜を物理的または化学的に除去する作業が不可欠です。
理由②:融点が低く、すぐに溶け落ちてしまう
アルミニウムの融点は約660℃であり、鉄の融点(約1535℃)と比較して非常に低いという特徴があります。
この低い融点は、溶接時の熱管理を難しくする大きな要因です。
溶接の熱によって、部材は適切な温度に達する前に一気に溶ける可能性があり、穴が開いたり、溶け落ちたりする失敗が起こりやすくなります。
特に、表面の酸化皮膜は融点が高いため、皮膜を溶かそうと高い熱量を加えると、内部の母材が意図せず溶け落ちてしまいます。
この温度管理の繊細さが、アルミ溶接の難易度を上げている一因と言えます。
理由③:熱が伝わりやすく、部材が歪みやすい
アルミニウムは熱伝導率が非常に高い金属で、鉄の約3倍も熱が伝わりやすい性質を持っています。
このため、溶接時に加えられた熱が溶接箇所だけでなく、部材全体に素早く拡散してしまいます。
熱が広範囲に及ぶことで、部材全体が膨張し、冷却される過程で収縮する際に大きな歪(ひずみ)が発生しやすくなります。
特に薄い板材の溶接では、この歪みの影響が顕著に現れ、部材が変形してしまうことが少なくありません。
歪みを最小限に抑えるためには、適切な溶接手順や治具の使用、入熱量のコントロールといった高度な技術が求められます。
理由④:ブローホール(気泡)による割れが発生しやすい
アルミニウムは溶融状態にあるとき、雰囲気中の水分などから分解された水素を吸収しやすい性質があります。
そして、溶けた金属が冷えて固まる際に、内部に取り込まれた水素ガスが放出され、ブローホールと呼ばれる空洞や気泡を形成します。
このブローホールは溶接部の強度を著しく低下させ、応力がかかった際に割れやクラックが発生する起点となります。
これを防ぐためには、溶接する部材や溶加材を十分に乾燥させ、湿気や汚れを徹底的に除去することが重要です。
また、シールドガスで溶融池を適切に保護する必要もあります。
アルミ部品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
アルミ溶接で使われる代表的な溶接方法
アルミニウムの溶接には、鉄やステンレスといった他の素材とは異なる、適した方法の選択が求められます。
一般的なアーク溶接以外にも、レーザー溶接など様々な種類がありますが、ここではDIYからプロの現場まで広く用いられる代表的な3つの溶接方法を紹介します。
それぞれの方法は、仕上がりの品質、作業速度、求められる技術レベルが異なります。
鉄やステンレスと共通する溶接方法もありますが、アルミという素材の特性を考慮した上で最適な種類を選ぶ必要があります。
精密で美しい仕上がりを目指せる「TIG溶接」
TIG溶接は、消耗しないタングステン電極と母材との間にアークを発生させて溶接する方法です。
溶接部はアルゴンやヘリウムといった不活性ガスでシールドされ、酸化を防ぎます。
アルミ溶接では、直流ではなく交流電源を用いるのが一般的で、交流のプラス極性の際に酸化皮膜を除去するクリーニング作用が得られるため、高品質な溶接が可能です。
作業者がトーチを操作し、もう片方の手で溶加棒を供給しながら進めるため、精密な作業に適しており、溶接ビードが非常に美しく仕上がります。
薄板から厚板まで幅広い用途に対応できるのが特徴です。
スピーディーな作業が得意な「半自動(MIG)溶接」
半自動溶接、特にMIG溶接は、トーチのトリガーを引くと溶接ワイヤーが自動的に供給され、同時にシールドガスが噴射される仕組みです。
連続的に溶接が行えるため、TIG溶接に比べて作業速度が格段に速く、生産性が高いのが最大のメリットです。
アルミのMIG溶接では、アルミ専用の溶接ワイヤー(A4043系やA5356系など)を使用します。
TIG溶接に比べるとスパッタ(火花)が発生しやすく、仕上がりの美しさでは劣るものの、厚板の溶接や長い距離を連続して溶接する作業に向いています。
基本的な溶接方法である「アーク溶接」
一般的にアーク溶接として知られる被覆アーク溶接は、フラックスという被覆材が塗布された溶接棒を用いて行います。
この被覆材が燃焼することでシールドガスを発生させ、溶融した金属を大気中の酸素などから保護します。
アルミ溶接を行う場合は、専用のアーク溶接棒が必要です。
ただし、TIG溶接やMIG溶接に比べてアークが不安定で、溶融池のコントロールが難しく、スラグの除去も必要になるため、現在ではアルミの溶接方法として主流ではありません。
設備が比較的安価で手軽な点が利点ですが、高い技術が求められます。
【方法別】アルミ溶接の具体的な手順と成功させるコツ
アルミを溶接する際は、単に溶接機を操作するだけでなく、適切な前処理や設定が製品の強度や仕上がりを大きく左右します。
ここでは、代表的な溶接方法ごとの具体的なやり方と、成功に導くためのコツを解説します。
練習を重ねることはもちろん重要ですが、母材に適した加工方法や溶接設計の知識も不可欠です。
正しい手順を理解し、適切な設定を行うことで、高品質な溶接を実現するための基礎を固められます。
TIG溶接でアルミをきれいに溶接する手順
TIG溶接で美しい仕上げを目指すには、まず溶接する板の表面を脱脂し、ステンレスブラシで酸化皮膜を除去します。
次に、板厚に合わせて溶接機の電流値を設定します。
例えば1mmや2mmといった薄板では低い電流、厚板では高い電流が必要です。
交流TIGを選択し、溶接を開始します。
トーチのノズルから出るシールドガスで溶融池を保護しながら、適切なタイミングで溶加棒を送り込む「棒入れ」の技術が重要です。
均一な速度でトーチを動かし、美しい裏波が出るように溶け込みをコントロールすることが、管やアングル、配管といった様々な形状の部材で高品質なビードを形成するコツです。
半自動(MIG)溶接で効率よく作業を進めるコツ
半自動(MIG)溶接を効率よく進めるためには、ワイヤーの安定した送給が最も重要です。
アルミニウムのワイヤーは柔らかく座屈しやすいため、ワイヤー送給装置からトーチまでの距離を短く保ち、滑りの良い専用のライナーやコンタクトチップを使用することが推奨されます。
また、適切な電圧と電流、ワイヤー送給速度の設定が不可欠で、これらがずれるとスパッタが多発したり、溶け込みが浅くなったりする原因となります。
トーチを少し押し気味の角度で構え、一定の速度で移動させることで、均一で安定したビードを形成できます。
アーク溶接でアルミを接合する際の注意点
アルミのアーク溶接は難易度が高いですが、いくつかの注意点を守ることで実施できます。
まず、アルミ専用の被覆アーク溶接棒は非常に湿気を吸いやすいため、使用直前に規定の温度と時間で必ず乾燥させる必要があります。
湿気を含んだまま使用すると、ブローホールの原因となります。
アークの発生が不安定になりがちなので、最初は捨て板などでアークを安定させてから本番の溶接に入ると良いでしょう。
溶接後に発生するスラグは、放置すると腐食の原因になるため、ワイヤーブラシなどで完全に取り除くことが重要です。
アルミ溶接でよくある失敗とその対策
アルミ溶接は特性上、様々な溶接不良や欠陥が発生しやすい作業です。
特に初心者の場合、溶け込みが浅かったり、溶接後しばらくしてから割れが生じたりといった失敗に直面することがあります。
ここでは、アルミ溶接で頻繁に見られる代表的な失敗例を取り上げ、その原因と具体的な対策について解説します。
これらのポイントを理解することで、欠陥の発生を未然に防ぎ、より高品質な溶接を目指せます。
溶け込み不良を改善するためのポイント
溶け込み不良は、溶接金属が母材に十分に溶け込んでいない状態で、強度不足の直接的な原因となります。
主な原因は、溶接前の表面処理不足による酸化皮膜の残存、電流値の低さ、溶接速度の速すぎなどが挙げられます。
対策としては、まずワイヤーブラシや研磨ディスクで溶接する面の酸化皮膜を完全に取り除くことが基本です。
溶接中に黒いススのようなものが発生する場合、酸化皮膜が除去しきれていない証拠です。
また、母材の裏面までしっかりと熱が伝わるよう、板厚に適した十分な電流を設定し、溶融池の状態を確認しながら適切な速度で溶接を進めることが改善のポイントです。
溶接後の割れを防ぐための対策
溶接後に発生する割れは、主に溶けた金属が冷えて固まる過程で生じる凝固割れです。
これはアルミニウム合金の組織的な特性に起因することが多く、特に高温での強度低下が激しい温度域で発生しやすくなります。
この割れを防ぐためには、母材の種類に適した溶加材を選ぶことが極めて重要です。
また、急激な加熱と冷却を避けるために、必要に応じて予熱や後熱を行い、冷却速度を緩やかにコントロールすることも有効な対策となります。
ビードの終端部にクレーターができやすいため、電流を徐々に下げてクレーターを適切に処理することも割れ防止に繋がります。
DIYでアルミ溶接は可能?難易度と注意点
個人がDIYでアルミ溶接に挑戦することは不可能ではありませんが、鉄の溶接に比べて難易度は格段に上がります。
その最大の理由は、適切な設備を揃えるハードルの高さです。
アルミ溶接には、交流出力が可能なTIG溶接機や、アルミ専用の半自動溶接機といった高価な溶接機が必要になります。
ホームセンターなどで手に入る安価な家庭用の溶接器では、アルミに対応していない場合がほとんどです。
また、溶接作業には専門的な知識と技術が求められ、特に資格は不要ですが、安全管理も含めて簡単ではありません。
まとめ
アルミ溶接は、特性から高い技術を要しますが、適切な方法と手順を理解すれば品質の高い接合が可能です。
DIYでの挑戦も魅力的ですが、A5052や6000番台といった合金の溶接、特に車やロードバイクのフレーム、マフラー、ホイール、エンジンケースといった重要部品の修理や、鋳物の肉盛り補修などは、専門の会社や工場への依頼が賢明です。
専門の溶接屋は、材質に合わせた溶接補修サービスを提供しており、近くのメーカーや修理工場で対応可能な場合もあります。
例えば新潟県など、地域に根差した高い技術を持つ会社も存在し、タンクの修理や鋳造品の肉盛など、個人の依頼にも対応しています。
NBKでは、燕三条の地場の特性を活かし、アルミ材の溶接も対応しております。
是非1度ご相談ください。