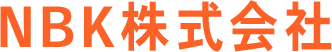めっきとは?種類や目的、方法の解説
めっきとは、金属や非金属などの材料の表面に、薄い金属の膜を形成する表面処理技術の一種です。
この技術を用いる目的は、製品の見た目を美しくする装飾性、錆や腐食から素材を保護する耐食性、そして電気伝導性や硬度といった新たな特性を与える機能性の付与など多岐にわたります。
この記事では、めっきの基本的な定義から、具体的な加工方法の種類と特徴、使用される金属ごとの特性について詳しく説明します。
メッキとは何か?基本をわかりやすく解説
メッキは金属または非金属の材料表面に、金属の薄い皮膜を電気的・化学的な方法で析出させる技術です。
一般的に「メッキ」とカタカナで表記されますが、その由来は「滅金(めっきん)」という言葉が変化したものという説があります。
これは、金以外の金属で金のような外観に仕上げることを指したと言われています。
JISの加工用語では「めっき」とひらがなで表記されるのが正式ですが、一般的にはカタカナ表記も広く使われています。
NBKではメッキまで全加工で製作を対応しております!ぜひお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
メッキを施す3つの主な目的
メッキの目的は、大きく分けて「装飾」「防食」「機能性」の3つに分類されます。
これらの目的は、製品の用途や求められる性能に応じて単独、あるいは複合的に適用されます。
例えば、自動車の部品では、美しい外観(装飾)と錆を防ぐ性能(防食)の両方が求められることがあります。
このように、メッキは様々な産業分野で製品の付加価値を高めるために不可欠な技術となっています。
目的1:製品の見た目を美しくする装飾性
メッキの目的の一つは、製品の見た目を向上させる装飾性です。
素材の表面に金や銀、クロムなどの金属皮膜を形成することで、特有の光沢や色彩を与え、高級感や美観を高めます。
この目的でメッキが利用される代表的な例が、ネックレス、指輪、リングといったアクセサリーです。
安価な金属を素地にして表面に金メッキを施すことで、コストを抑えながら金製品のような外観を実現します。
また、自動車のエンブレムや家電製品のスイッチ類など、身の回りの多くの工業製品にも、デザイン性を高めるために装飾メッキが施されています。
目的2:サビや腐食から素材を守る耐食性
鉄などの金属は、空気中の酸素や水分に触れると錆びてしまい、強度が低下するなどの劣化を引き起こします。
メッキは、このような腐食から素材を保護する目的でも広く用いられます。
錆びやすい素材の表面を、ニッケルやクロム、亜鉛といった錆びにくい金属の膜で覆うことで、腐食の原因となる物質との接触を遮断し、製品の寿命を延ばします。
特に、鉄鋼材料に施される亜鉛めっき(錆めっき)は、亜鉛が鉄の代わりに犠牲となって溶ける「犠牲防食作用」により、皮膜に傷がついても高い防食効果を維持するのが特徴です。
目的3:電気伝導性などの新たな機能を加える機能性
メッキは、素材が元々持っていない新しい機能を付与するためにも利用されます。
例えば、プラスチックのような電気を通さない素材に銅やニッケルのメッキを施して導電性を持たせたり、金属部品の表面に硬質クロムメッキを施して耐摩耗性を向上させたりします。
その他にも、はんだ付け性を良くする錫メッキ、摩擦を低減させる潤滑メッキ、金型から製品を剥がれやすくする離型性メッキなど、その用途は多岐にわたります。
これらの機能性メッキは、電子部品や半導体、自動車、航空宇宙分野など、高い性能が要求される製品に不可欠です。
メッキの加工方法による2つの分類
メッキの加工方法は、皮膜を形成する際の環境によって、液体中で行う「湿式メッキ」と、気体中で行う「乾式メッキ」の2種に大別されます。
どちらの方法を選択するかは、母材の種類、製品の形状、求められる皮膜の特性や厚さ、生産コストなどを総合的に考慮して決定されます。
それぞれの方法には異なる原理や流れがあり、特徴に応じた使い分けが行われています。
湿式メッキ:液体(水溶液)中で皮膜を形成する方法
湿式メッキは、金属塩を溶かした水溶液(メッキ液)の中に製品を浸漬し、化学的または電気的な作用によって金属イオンを還元させ、製品表面に金属膜を析出させる方法です。
この方法では、溶液中の金属イオンの濃度や価数、温度、pH、添加剤の種類などが、できあがる皮膜の品質や特性に大きく影響します。
湿式メッキは、外部から電流を供給する「電気メッキ」と、溶液中の還元剤の化学反応を利用する「無電解メッキ」の2つにさらに分類され、それぞれに特徴と用途があります。
電気メッキ:外部電源を利用して金属を析出させる
電気メッキは、工業的に最も多く利用されている一般的なメッキ方法です。
メッキしたい金属を陽極(+)、メッキをつけたい製品を陰極(-)としてメッキ液に浸し、外部から直流電流を流します。
すると、陽極の金属がイオンとなって液中に溶け出し、陰極である製品の表面に引き寄せられて電子を受け取り、金属として析出することで皮膜が形成されます。
この方法は成膜速度が速く、比較的厚い膜を安価に作れる利点があります。
装飾品から工業製品まで、非常に幅広い分野で用いられています。
無電解メッキ(化学メッキ):化学反応で皮膜を作る
無電解メッキは、外部電源を使用せず、メッキ液に含まれる還元剤の作用によって金属イオンを還元し、皮膜を析出させる化学的な方法です。
この反応は製品表面で自己触媒的に進行するため、電流が不要です。
電気を通さないプラスチックやセラミックスといった素材にもメッキを施せる点が大きな特長です。
また、電気メッキのように電流分布の影響を受けないため、複雑な形状の製品やパイプの内側などにも均一な厚さの皮膜を形成できます。
代表的な例として、寸法精度や硬度が求められる部品に用いられる無電解ニッケルメッキが挙げられます。
乾式メッキ:気体(真空)中で皮膜を形成する方法
乾式メッキは、真空容器内などの気体中で、物理的または化学的なプロセスを用いて材料表面に薄膜を形成する技術の総称です。
液体を使用しないため、湿式メッキでは困難な高融点の金属や合金、セラミックスといった多様な材料で皮膜を形成できます。
一般的に、湿式メッキに比べて素材との密着性が高く、非常に硬質で緻密な層を作ることが可能です。
乾式メッキには、真空蒸着(PVD)、化学気相成長(CVD)、溶融メッキといった異なる原理に基づく複数の方法が含まれます。
真空蒸着(PVD):金属を蒸発させて付着させる
真空蒸着(PVD: Physical Vapor Deposition)は、高真空状態に保たれた容器内で、成膜材料となる金属などを加熱して蒸発させ、気化した粒子を対象物の表面に付着させて薄膜を形成する方法です。
蒸発した粒子は真空中を直進して対象物に到達し、冷却されて固体膜となります。
この方法により、高純度で緻密な皮膜を得ることが可能です。
スパッタリングやイオンプレーティングなどもPVDの一種で、物理的なエネルギーを利用して成膜材料を気化またはイオン化させ、対象物に衝突させて成膜する点で共通しています。
化学気相成長(CVD):化学反応ガスで膜を形成する
化学気相成長(CVD: Chemical Vapor Deposition)は、皮膜の構成元素を含む原料ガスを高温に加熱した対象物の近傍に供給し、表面での熱分解や化学反応によって薄膜を堆積させる方法です。
ガスの種類や流量、反応温度、圧力などを精密に制御することで、目的とする組成や結晶構造を持つ高品質な膜を作製できます。
PVDに比べて回り込み性が良く、複雑な形状の対象物にも比較的均一な膜を形成できる利点があります。
ただし、プロセスが高温になることや、シアン化合物のような有毒ガスを使用する場合があるため、装置や取り扱いには注意が必要です。
溶融メッキ:溶かした金属に浸してコーティングする
溶融メッキは、亜鉛や錫、アルミニウムなどをその融点以上に加熱して溶かした金属浴の中に、鋼材などの製品を浸漬し、表面に皮膜を形成する方法です。
製品を引き上げた後、付着した溶融金属が冷えて固まることでコーティングが完了します。
この方法の代表例が、鉄鋼製品の防食に広く用いられる溶融亜鉛メッキです。
比較的厚い膜を効率的に形成でき、高い耐久性と防食性が得られるのが特徴です。
メッキ後に、耐食性をさらに高めるためのクロメート処理が施されることもあり、これをユニクロメッキと呼ぶこともあります。
NBKではメッキまで全加工で製作を対応しております!ぜひお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
メッキで使われる代表的な金属の種類と特徴
メッキに用いられる金属の種類によって、製品に付与される特性は大きく異なります。
美しい光沢、錆びにくさ、電気の通しやすさ、硬さなど、メッキの特徴は多岐にわたります。
そのため、製品の用途や目的に合わせて最適な金属皮膜を選択することが重要です。
ここでは、工業製品や装飾品などで広く利用されている代表的な金属メッキを例に挙げ、それぞれの特徴と主な使われ方を解説します。
金メッキ(Au):優れた耐食性と導電性
金メッキは、化学的に極めて安定で酸化や腐食に強いという優れた耐食性を持ちます。
これにより、長期間にわたって美しい輝きと性能を保つことが可能です。
また、金は電気伝導性が高く、接触抵抗が低い特性も持っているため、電子部品のコネクタや端子、プリント基板の接点部分など、信頼性が要求される箇所に広く利用されます。
装飾品としても価値が高く、高級感を演出するために施されます。
一般的にメッキの文脈で「と金」という言葉が使われる場合、純金または金合金による皮膜を指します。
銀メッキ(Ag):高い導電性と装飾性
銀メッキは、すべての金属の中で最も高い電気伝導性と熱伝導性を誇ります。
その特性から、高周波を扱う電子部品やスイッチの接点など、優れた導電性が求められる用途に不可欠です。
また、銀特有の美しい白色の輝きは、カトラリーやアクセサリー、管楽器などの装飾目的でも重宝されます。
しかし、銀は空気中の硫黄分と反応して黒く変色しやすいという欠点があります。
この変色を防ぐため、銀メッキの上に変色防止処理を施したり、さらに耐食性の高いロジウムなどで薄くコーティングするロジウムメッキが行われたりします。
銅メッキ(Cu):下地処理や熱伝導性向上に利用
銅メッキは、良好な電気伝導性と熱伝導性を持ちながら比較的安価であるため、幅広い用途で活用されています。
特に、他のメッキを施す際の下地としての役割が重要です。
素材と上層のメッキ皮膜との密着性を向上させたり、素材表面の微細な凹凸を埋めて平滑化したりする効果があります。
例えば、プラスチックのような非導電性素材へのメッキでは、まず無電解銅メッキで導電層を形成し、その上にニッケルメッキなどを重ねます。
また、プリント基板の配線パターンや電線の端子など、導電性を直接利用する用途にも用いられます。
ニッケルメッキ(Ni):硬度と耐食性を与える下地・仕上げ
ニッケルメッキは、適度な硬度と優れた耐食性を持ち、美しい銀白色の外観から、装飾、防食、機能性のすべての目的で広く利用されます。
クロムメッキの下地として使われることが多いですが、ニッケルメッキ単体で最終仕上げとしても用いられます。
光沢剤の有無や種類によって外観や特性が異なり、JIS規格では光沢の度合いに応じて1号メッキから3号メッキなどに分類されます。
電気を使わない無電解ニッケルメッキは、均一な膜厚と高い硬度が得られるため、精密な機械部品などに適しています。
クロムメッキ(Cr):美しい光沢と高い硬度が特徴
クロムメッキは、青みがかった特有の銀白色光沢を持ち、非常に高い硬度と優れた耐摩耗性、耐食性を兼ね備えています。
用途によって、薄く施す「装飾クロムメッキ」と、厚く施す「硬質クロムメッキ」に大別されます。
前者は自動車のエンブレムや水道の蛇口など外観部品に、後者はピストンリングや金型といった高い耐久性が求められる機械部品に利用されます。
近年では、環境負荷の観点から従来の六価クロムに代わり三価クロムを用いたメッキや、意匠性の高い黒色の外観を持つ黒クロムメッキの利用も増えています。
錫メッキ(Sn):はんだ付け性や安全性が高い
錫メッキの最も重要な特徴は、はんだとの濡れ性が非常に良い、優れたはんだ付け性です。
この特性から、電子部品のリード線やコネクタの端子、プリント基板など、はんだによる接続が行われる部分に広く採用されています。
また、錫は人体に対する毒性が極めて低く安全な金属であるため、飲料用の缶詰の内面コーティングや調理器具など、食品に直接触れる製品にも利用されます。
耐食性も良好で、ステンレス鋼のようなはんだ付けが難しい素材にも、下地処理を施した上で錫メッキを行うことで、はんだ付け性を付与できます。
製品の形状に合わせたメッキの加工方法
メッキをする際には、製品の形状や大きさ、生産量に応じて最適な加工方法を選ぶことが品質とコストを両立させる上で重要です。
製品をどのように保持し、処理するかによって、仕上がりの均一性や生産効率が大きく変わります。
ここでは、工業的に広く用いられている「ラックメッキ」「バレルメッキ」「フープメッキ」という3つの代表的な加工方法について、それぞれの特徴を解説します。
ラックメッキ:製品を治具に固定して処理する方法
ラックメッキは、製品を「ラック」と呼ばれる専用の治具に一つひとつ取り付けて固定し、メッキ槽に浸漬する加工方法です。
製品同士が接触することがないため、打痕や傷がつくのを防ぎ、美しい外観を保つことができます。
また、製品の位置や向きをコントロールしやすく、安定した電流供給が可能なため、膜厚の均一性が高く、高品質な仕上がりが得られます。
このため、外観が重視される装飾部品や、寸法精度が厳しく求められる精密部品、大型の製品に適しています。
治具には導電性のあるステンレスやチタンが使われることが多く、製品の形状に合わせて設計されます。
バレルメッキ:樽型の容器で回転させながら処理する方法
バレルメッキは、バレルと呼ばれる穴の開いた樽型の回転容器の中に、小さな製品を大量に入れて、回転させながらメッキ処理を行う方法です。
容器を回転させることで製品が常にかき混ぜられ、すべての表面にメッキ液が触れるため、一度に多くの製品を効率良く処理することが可能です。
このため、ネジやボルト、ナットといった小型で安価な部品の大量生産に適しています。
ただし、製品同士がぶつかり合うため、傷がつきやすく、複雑な形状の製品や高い外観品質が求められるものには向きません。
フープメッキ(リールtoリールメッキ):帯状の素材を連続で処理する方法
フープメッキは、プレス加工される前の帯状の金属材料(フープ材)や、リールに巻かれた連続的な製品を、装置内を通過させながら連続的にメッキ処理を行う方法で、「リールtoリールメッキ」とも呼ばれます。
材料をリールから巻き出し、脱脂、メッキ、洗浄、乾燥といった一連の工程をライン上で連続的に行い、処理後に再びリールに巻き取るという流れで進められます。
電子部品のコネクタ端子など、同じ形状の製品を大量かつ高速に生産する場合に採用されます。
必要な箇所にだけメッキを施す部分メッキも可能で、金などの貴金属の使用量を抑えることができます。
知っておきたいメッキのメリット
メッキ技術は、多くのメリットから、自動車、電子機器、建築、装飾品といった幅広い産業分野で不可欠な存在となっています。
素材そのものの特性を活かしつつ、表面に新たな価値を付加できる点が、この技術が広く利用される大きな理由です。
ここでは、メッキがもたらす主要な利点について解説します。
多様な素材に機能を追加できる点が強み
メッキが持つ最大のメリットは、母材となる素材の種類に捉われず、表面に多様な機能を付加できる点です。
例えば、安価で加工しやすい鉄に、高価な金属であるクロムやニッケルのメッキを施すことで、優れた耐食性や美しい光沢を与えることが可能です。
また、無電解メッキ技術の発展により、プラスチックやセラミックスなどの非金属材料にも導電性や金属光沢を持たせることができます。
これにより、製品の軽量化と高機能化を同時に実現するなど、材料の選択肢が広がり、製品設計の自由度が大幅に向上します。
注意すべきメッキのデメリット
メッキは多くの利点を持つ一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。
これらの課題を事前に理解しておくことは、メッキの品質を確保し、期待される性能を確実に得るために重要です。
均一な膜厚の維持や剥がれのリスクがある
メッキ処理における技術的な課題として、膜厚の均一性を保つことの難しさが挙げられます。
特に電気メッキでは、製品の角や先端部分に電気が集中しやすく、皮膜が厚くなる一方で、窪んだ部分や内面は皮膜が薄くなる傾向があります。
この膜厚の不均一さは、部品の寸法精度や性能に影響を及ぼす可能性があります。
また、素材とメッキ皮膜との密着性が不十分な場合、使用中に皮膜が剥がれてしまうことがあります。
剥がれは、素材表面の汚れや酸化膜を除去する前処理の不足などが主な原因であり、全工程における徹底した品質管理が求められます。
メッキと他の表面処理方法の違いとは?
材料の表面に特定の機能を付与したり、性質を改善したりする技術は「表面処理」と総称されます。
メッキもその表面処理技術の一つですが、他にも塗装やアルマイトなど様々な方法が存在します。
ここでは、代表的な表面処理である塗装とアルマイトを取り上げ、メッキとの原理や特性の違いについて比較解説します。
塗装との違い:皮膜の密着性と硬度
塗装は、塗料を製品表面に塗布し、乾燥・硬化させることで有機物の皮膜(塗膜)を形成する技術です。
塗料の色や種類が豊富なため、デザインの自由度が高いのが特徴です。
一方、メッキは金属皮膜を形成するため、一般的に塗膜よりも硬度が高く、耐摩耗性に優れます。
また、密着性においても、原子レベルで素材と結合するメッキの方が、物理的に付着している塗装よりも強固な場合が多いです。
ただし、メッキで表現できる色彩は金属固有の色に限定されるなど、両者にはそれぞれ得意な領域があります。
アルマイトとの違い:処理できる金属の種類と原理
アルマイトは陽極酸化処理とも呼ばれ、アルミニウム製品を電解液中で陽極として電気を流し、表面に酸化アルミニウムの硬い皮膜を生成させる技術です。
メッキが素材の上に別の金属を重ねるのに対し、アルマイトは素材であるアルミニウム自体を化学的に変化させて皮膜を作るという点で、その原理が根本的に異なります。
このため、アルマイト処理はアルミニウムとその合金にしか適用できません。
それに対してメッキは、鉄、銅、亜鉛など多様な金属はもちろん、適切な前処理を行えばプラスチックなどの非金属にも施すことができ、適用範囲が広いのが特徴です。
まとめ
メッキは、材料の表面に金属の薄膜を形成することで、装飾性の向上、錆や腐食からの保護、電気的・機械的特性の付与といった多様な目的を達成する表面処理技術です。
加工方法には溶液中で行う湿式と真空中などで行う乾式があり、製品の材質や形状、求める性能に応じて最適な方法が選択されます。
使用する金属によっても特性が大きく異なるため、各種の用語や技術の原理を理解することが重要です。
NBKではメッキまで全加工で製作を対応しております!ぜひお任せください!
<a class=”link-button-orange” href=”https://www.niigata-buhinkakou.com/contact/”>お問い合わせはこちら</a>
<a class=”link-button-orange” href=”https://www.niigata-buhinkakou.com/download//”>資料ダウンロードはこちら</a>