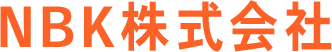ステンレス鋼(SUS)とは?種類ごとの特徴や錆びないメリットを解説
ステンレス鋼とは、鉄を主成分としながらも錆びにくい性質を持つ合金鋼の一種です。
この「錆びない」という大きなメリットから、私たちの身の回りにある製品から産業分野まで幅広く活用されています。
ステンレス鋼には多くの種類があり、それぞれに異なる特徴を持ちます。
この記事では、ステンレス鋼の基本的な特徴から、耐食性の仕組み、用途に応じた種類の選び方までを網羅的に解説し、その多岐にわたる利点と注意点を明らかにします。
ステンレス鋼(SUS)とは?基本的な特徴を解説
ステンレス鋼は、英語の「StainlessSteel」が名前の由来であり、直訳すると「錆びない鋼」という意味を持ちます。
日本産業規格(JIS)では、その略称として「SUS(サス)」が用いられ、これは「SteelUseStainless」の略です。
この金属素材は、主成分である鉄(鋼)に、一定量以上のクロムやニッケルといった成分を添加して作られた合金鋼を指します。
19世紀初頭から研究が始まり、20世紀初頭にイギリスで発明された歴史を持つ素材で、耐食性の高さから多様な製品に利用されています。
ステンレスが錆びにくいのはなぜ?不動態皮膜の仕組み
ステンレス鋼が錆びにくい理由は、含有されるクロムの働きにあります。
クロムが空気中や水中の酸素と瞬時に反応し、素材の表面に非常に薄く、緻密で安定した「不動態皮膜」と呼ばれる酸化皮膜を形成します。
この不動態皮膜が保護膜として機能し、鋼材内部への酸素の侵入を防ぐことで、鉄の酸化、すなわち錆の発生を抑制します。
万が一、表面に傷がついてこの皮膜が破壊されたとしても、周囲に酸素があれば自己修復する性質を持っているため、耐食性が長期間持続するのです。
ステンレス鋼(SUS)を使用する4つのメリット
ステンレス鋼は、錆びにくいという最大の特徴に加え、多くの優れたメリットを持っています。
その優れた強度や耐久性、高温から低温まで幅広い温度域に対応できる耐熱性、そして衛生的で美しい外観を長期間維持できる意匠性など、その利点は多岐にわたります。
さらに、特別な表面処理を必要としないため、メンテナンスが容易であることも大きな利点です。
これらの特性により、家庭用品から最先端の産業機械まで、非常に幅広い分野で不可欠な材料として採用されています。
1. 優れた強度と耐久性を誇る
ステンレス鋼は、鉄を主成分とする合金であるため、元来高い機械的強度を備えています。
特にオーステナイト系のステンレスは、力を加えて変形させると硬化する「加工硬化」という性質が顕著です。
この特性は加工硬化指数(n値)という指標で表され、n値が大きいほど粘り強く、破断しにくい材料であることを示します。
また、炭素鋼などと比較しても高い硬度を持つため、表面に傷がつきにくく、摩耗にも強いです。
このような優れた強度と耐久性により、長期間にわたって性能を維持する必要がある構造部材や機械部品に広く利用されています。
2. 高温や低温に強く熱を保ちやすい
ステンレス鋼は、優れた耐熱性を持ち、高温環境下でも強度の低下が少ないという特徴があります。
添加されたクロムが高温での酸化を防ぎ、表面にスケールと呼ばれる酸化物が生成されにくいためです。
一方で、オーステナイト系のステンレスは極低温環境下でも脆くならず、靭性を保つ特性も備えています。
また、一般的な鋼材に比べて熱膨張率が比較的小さく、急激な温度変化による変形も抑えられます。
この熱に対する強さから、厨房機器や化学プラント設備、さらにはロケットのエンジン部品など、過酷な温度条件下で使用される多様な分野で活用されています。
3. 衛生的で美しい見た目を維持できる
ステンレス鋼の表面は緻密で非多孔質であるため、汚れが付着しにくく、細菌の繁殖を抑制します。
この衛生的な特性から、キッチンの流し台(シンク)や調理台の天板、包丁、食器など、食品に直接触れる製品に多く採用されています。
また、水筒やタンブラーに使用される場合、金属臭が飲み物に移りにくい点も利点です。
ただし、塩分や酸性の強いものを長時間付着させたままにすることは、錆の原因となりうるためです。
耐食性が高いため、金属イオンが溶出しにくく、美しい金属光沢を長期間維持できることから、意匠性が求められる場面でも重宝されます。
4. メンテナンスが簡単で長期間使用できる
ステンレス鋼は、その優れた耐食性により、塗装やメッキといった防錆処理を施す必要が基本的にありません。
これにより、製造コストの削減だけでなく、使用開始後の再塗装などのメンテナンスにかかる手間や費用を大幅に低減できます。
日常的な手入れは、中性洗剤と柔らかいスポンジで洗浄し、水気を拭き取るだけで十分です。
万が一、表面に軽微な傷や汚れが付着した場合でも、研磨による補修が比較的容易に行えます。
このメンテナンスの容易さと素材自体の耐久性が、建築物の内外装や公共設備など、長期にわたる使用が前提とされる用途に適しています。
知っておきたいステンレス鋼(SUS)のデメリットと注意点
多くの優れた特性を持つステンレス鋼ですが、あらゆる状況で万能なわけではなく、いくつかのデメリットや使用上の注意点が存在します。
「錆びない」というイメージが強いものの、特定の環境下では腐食することもあります。
また、その高い強度や硬さが、逆に加工の難しさにつながる側面も持ち合わせています。
これらのデメリットを正しく理解し、用途や環境に応じて適切な材質選定と取り扱いを行うことで、ステンレス鋼の性能を最大限に引き出すことができます。
1. 条件によっては錆が発生することもある
ステンレス鋼は「錆びない鋼」ではなく「錆びにくい鋼」であり、その耐食性には限界があります。
表面の不動態皮膜が破壊され、自己修復が追いつかない環境に置かれると錆びることがあります。
例えば、海水や潮風に含まれる塩化物イオンは不動態皮膜を局部的に破壊し、孔食と呼ばれる点状の腐食を引き起こします。
また、洗浄薬品などに含まれる強い酸に長時間触れることも錆の原因です。
さらに、鉄粉などが付着した状態で水分に触れると、その鉄粉の錆が移る「もらい錆」という現象も発生します。
これらの腐食を防ぐには、使用環境に適した鋼種の選択と定期的な清掃が不可欠です。
2. 硬くて伸びにくいため加工が難しい
ステンレス鋼は高い強度と靭性を持つ反面、加工が難しい材料として知られています。
切削加工で材料を削る際には、その硬さから工具の刃が摩耗しやすく、加工時に発生する熱でさらに硬くなる「加工硬化」も起こりやすいため、適切な工具選定や加工速度の設定が求められます。
また、板材を曲げるプレス加工や曲げ加工では、一般的な鋼材よりも大きな力が必要となり、加工後に元の形状に戻ろうとする「スプリングバック」も大きくなります。
溶接においても、熱伝導率の低さから局所的に熱がこもりやすく、歪みや変形が生じやすいため、高度な技術が必要です。
3. 熱が伝わりにくく放熱性も低い
ステンレス鋼のデメリットの一つに、熱伝導率の低さが挙げられます。
これは、鉄やアルミニウム、銅といった他の金属材料と比較して熱が伝わりにくい性質を意味します。
この特性は、保温性が求められる魔法瓶や鍋にとってはメリットとなりますが、フライパンのように熱を素早く均一に伝える必要がある調理器具では、焼きムラの原因になり得ます。
そのため、調理器具では熱伝導率の高いアルミニウムをステンレスで挟んだ多層鋼が用いられることもあります。
また、放熱性が低いことから、電子機器の筐体やヒートシンクなど、効率的な排熱が求められる部品への使用にはあまり適していません。
4. 「焼き付き(かじり)」が起こりやすい
ステンレス鋼製のボルトとナットを締め付ける際、「焼き付き(かじり)」と呼ばれる固着現象が発生しやすい点に注意が必要です。
これは、部材同士が擦れ合う際に生じる摩擦熱によって表面の不動態皮膜が破壊され、金属面が直接触れ合うことで融着してしまう現象を指します。
ステンレスは、他の金属に比べて摩擦係数が高く、熱伝導率が低いために発生した熱が逃げにくいという性質があり、焼き付きの要因となります。
一度焼き付きが起こると、取り外しが極めて困難になり、部品を破壊せざるを得ない場合もあります。
これを防ぐためには、潤滑剤を塗布する、締め付け速度を遅くするなどの対策が有効です。
【系統別】ステンレス鋼(SUS)の代表的な種類と特徴
ステンレス鋼と一括りに言っても、その種類は多岐にわたります。
成分の配合比率や内部の金属組織によって、オーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系といった系統に大別されます。
これらの系統ごとに、耐食性、強度、磁性の有無、加工性、そして価格などが大きく異なります。
そのため、製品の用途や使用される環境、求められる性能に応じて、最適な種類のステンレス鋼を選定することが重要です。
ここでは、それぞれの系統の代表的な鋼種とその特徴について解説します。
オーステナイト系ステンレス:最も一般的な種類
オーステナイト系は、ステンレス鋼の中で最も生産量が多く、広く使用されている種類です。
主成分のクロムに加えてニッケルを含有することで、非常に優れた耐食性と靭性、そして良好な加工性を実現しています。
代表的な鋼種であるSUS304は、クロム18%、ニッケル8%を含むことから「18-8ステンレス」とも呼ばれます。
さらに耐食性を高めるためにモリブデンを添加したのがSUS316です。
また、被削性を向上させたSUS303のような種類も存在します。
ニッケルの含有量を高めた「18-10」はより耐食性に優れます。
磁性を持たず、溶接性にも優れているのが特徴です。
フェライト系ステンレス:磁性があり安価
フェライト系ステンレスは、主成分がクロムであり、高価なニッケルを含まないか、含んでもごく微量である点が特徴です。
代表的な鋼種にはSUS430があり、クロムを約18%含むことから「18-0ステンレス」とも呼ばれます。
ニッケルを含まないため、オーステナイト系と比較して安価で、コストパフォーマンスに優れます。
オーステナイト系とは異なり磁性を持つため、磁石がつくという性質があります。
耐食性はオーステナイト系に一歩譲りますが、一般的な屋内環境などでは十分な性能を発揮します。
加工性も比較的良好で、厨房機器の部品や自動車のマフラー、建築内装材などに広く利用されています。
SUS403もこの系統の鋼種です。
マルテンサイト系ステンレス:高強度で硬い
マルテンサイト系ステンレスは、クロムを主成分としますが、他の系統に比べて炭素の含有量が多いのが特徴です。
この系統の最大の利点は、焼入れ・焼戻しといった熱処理を施すことで、金属組織が変化し、非常に高い硬度と強度を得られる点にあります。
この優れた機械的性質を活かし、刃物、工業用カッター、タービンブレード、シャフトなど、高い耐摩耗性や強度が求められる部品に用いられます。
代表的な鋼種としてはSUS410が挙げられます。
ただし、その硬さと引き換えに、耐食性はオーステナイト系やフェライト系よりも劣るため、腐食しやすい環境での使用には注意が必要です。
オーステナイト・フェライト系(二相系):強度と耐食性を両立
オーステナイト・フェライト系は二相系ステンレスとも呼ばれその名の通りオーステナイトとフェライトの二つの金属組織が混在しているのが特徴です
この複合的な組織によりオーステナイト系の持つ優れた耐食性とフェライト系の持つ高い強度を両立させています
特に海水などの塩化物イオンが存在する環境下で発生しやすい孔食や応力腐食割れに対する耐性が極めて高いです
そのため化学プラントの設備や海水淡水化装置など過酷な腐食環境でその真価を発揮します
また銅などを添加し析出硬化処理でさらに強度を高めたSUS630のような析出硬化系も存在します
まとめ
ステンレス鋼はその優れた特性から様々な形状で供給され多岐にわたる分野で活用されています。
製品の素材としては薄板から厚さ6mmを超えるような板筒状のパイプなどが流通し部品としてはネジやワッシャーナットなどが広く使われています。
これらの素材は自動車のマフラーや建材精密機器の筐体などあらゆる製品の基盤となります。
通常は素材の質感を活かして使用されますが意匠性や特定の機能を付与するために塗装や特殊なコーティングメッキなどの表面処理が施されることもあります。
またエッチングによる微細な模様加工や研磨による鏡面仕上げなども可能です。
このようにステンレス鋼は素材の種類から板厚形状表面処理まで用途に応じた幅広い選択肢が存在します。
ステンレス部品でコストダウン・お困りの案件がありましたら、右側の【お問い合わせフォーム】よりご相談ください。