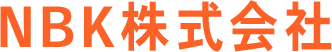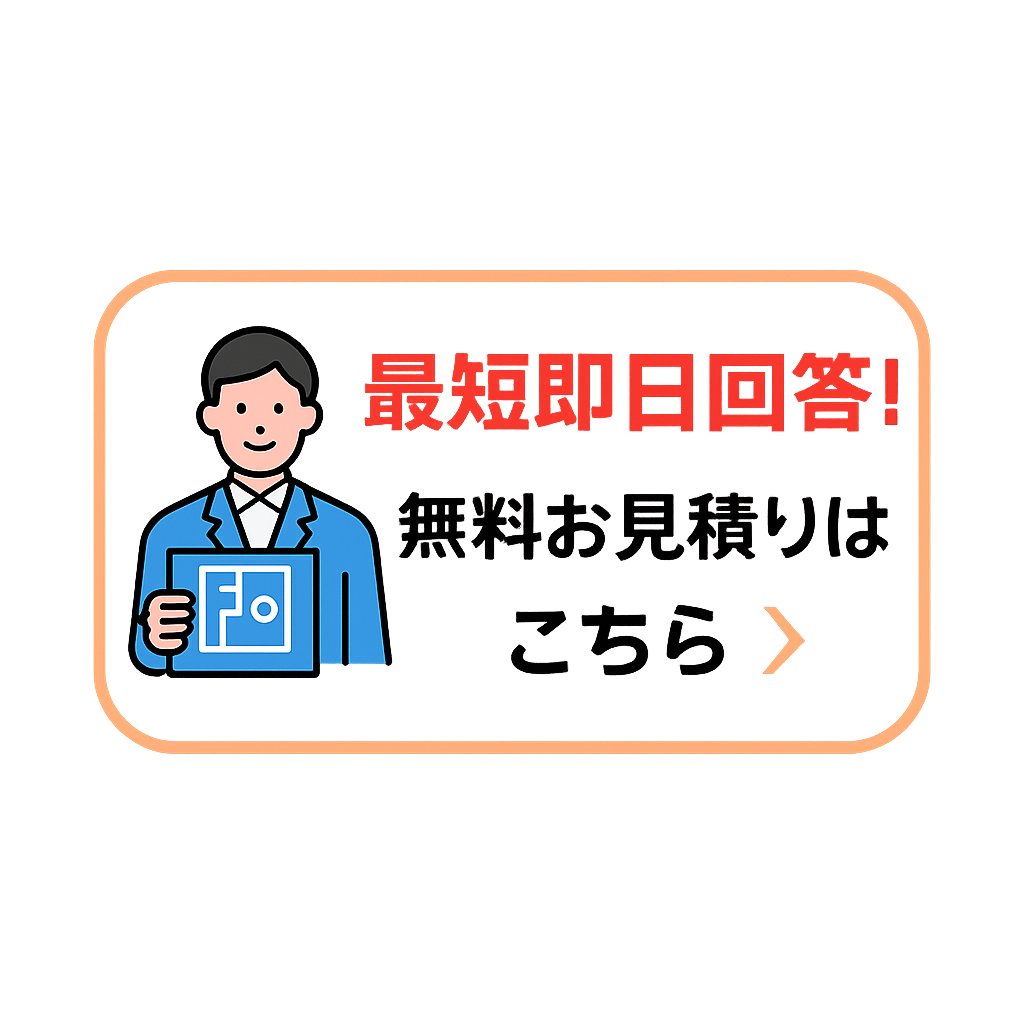部品の加工や調達の関係で平面研削盤の使用を検討している方はいらっしゃるでしょうか。
使ったことがない機械をいきなり工場に導入するというのは厳しいですよね。
そこで今回は、平面研削盤とは何か、どんな用途に使うのかについて紹介したいと思います。
□平面研削とは
ここでは平面研削とは何かについて紹介したいと思います。
まずは前提となる研削加工についてです。
研削加工とは、回転する砥石で加工する予定の素材の凹凸を削り取ることで、滑らかにする加工です。
削り取ると聞くと、切削加工なのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。
切削加工との大きな違いは、刃物の有無です。
切削加工は刃物を使用して削りますが、研削加工は砥石を使用するという違いがあります。
研削加工について紹介したところで、平面研削とは何かについて説明していきます。
平面研削とは、砥石を使用しながら素材の表面を研削して、高い平面度と並行度を実現する加工です。
似たような加工に平面研磨があるけれど、何が違うのかと思った方もいらっしゃるでしょう。
研削と研磨はどちらも素材の表面の仕上がりを良くするという点では同じような働きをしています。
しかし、実際は細かな部分で違いがあります。
研削は回転する砥石を使用して物理的に素材の表面を削っていきます。
一方で、研磨は流動する粒子を使用して素材の表面を削っていきます。
研削と研磨では削り取る量に違いがあります。
研磨は削る量が非常に少ないので、素材の形状が大きく変化することはありません。
□平面研削盤の種類について紹介!
ここでは4種類の平面研削盤について紹介したいと思います。
4種類それぞれの特徴についてまとめているので、選定時の参考になれば幸いです。
・立軸角テーブル型
こちらはテーブル面に対して主軸が垂直方向に向いています。
角テーブルを備えています。
ワークを固定したテーブルを左右に動かすことで砥石をワークに接触させます。
砥石の側面で研削することで大きな面積の加工ができるため、効率良く荒加工ができます。
また、こちらのタイプは長尺のワークの加工に最適です。
・立軸円テーブル型
こちらもテーブル面に対して主軸が垂直方向に向いています。
円テーブルを備えており、ロータリー研削盤と呼ばれることもあります。
円形テーブルにワークを複数並べながらテーブルを回転させて加工を行います。
こちらのタイプでは、複数のワークを高い精度で同じ厚みに加工できます。
そのため、小さな部品の大量生産に向いています。
・横軸角テーブル型
こちらはテーブル面に対して主軸が平行についており、テーブルを水平方向に動かすことで加工を行います。
平面研削盤の中で一番普及率の高いものです。
面粗さが良好なため、仕上げ加工ができます。
また、立方体や直方体のワークへの加工に適しています。
・横軸円テーブル型
こちらはテーブル面に対して主軸が平行で、円形テーブルを備えている研削盤です。
横軸ロータリーと呼ばれることもあります。
立軸円テーブル型と同じように小さな部品の量産に向いています。
また、円形や正方形のワークの加工に採用されることが多いです。
□平面研削で発生しやすい問題とは
平面研削をする際によく発生する問題についても押さえておきたいと思います。
事前にどのような問題が起きやすいのかを把握しているのとそうでないのとでは、その後の対応に大きな差が生まれます。
そのため、ここで紹介する内容はぜひ覚えていってくださいね。
1つ目の問題は、びびりです。
こちらは平面検索の中でもトップクラスに発生しやすい問題です。
びびりとは、砥石の動きが素材に写ってしまっている状態のことを指します。
砥石の振動によって模様ができたようなびびりは、ほとんどの場合振動が原因です。
振動が発生するのは、軸のセッティングが緩かったり、砥石目の粗さが適切でなかったりするためです。
素材に合わせて適切な砥石を選択し、入念なセッティングをしてくださいね。
・キズと送りマーク
こちらもびびりに続いて発生しやすい問題です。
砥石フランジのゆるみや切削液の中の不純物、砥石の粒度などが原因であることが多いです。
セッティングミスによる問題は事前の確認で防止できるので、しっかりとチェックしましょう。
・ワーク精度不良
砥石が不適合、研削液の潤滑性不足、研削作業の調整ミスなどが主な原因です。
精度不良に関してもセッティングミスが大半の原因です。
潤滑性の不足は割れや焼けの原因になるので、気をつけましょう。
・砥石の破損
フランジのセッティングや切削速度の超過、過熱が原因です。
砥石が3つ以上の破片に割れる場合は、砥石側面に過剰な負荷がかかっている可能性が高いです。
□まとめ
今回は、平面研削盤とは何か、どんな用途に使うのかについて紹介しました。
平面研削盤の種類からそれぞれの用途まで理解していただけたでしょうか。
発生しやすい問題とその対策についてもぜひ覚えておいてくださいね。