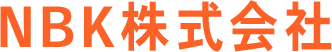ヘリサート(ねじインサート)とは?
ヘリサートとは、タップ加工で開けられためねじの補強や補修に用いられる、スプリング状のねじインサートです。特にアルミなどの柔らかい金属や樹脂など、直接ねじを切ると強度が保てない素材のめねじを強化する際に使用されます。また、壊れてしまったねじ山を補修し、再び使用できるようにする役割も担っています。この技術は、製品の信頼性向上や寿命延長に貢献するものです。
ヘリサートの概要
ヘリサートとは、ねじ山の補修や補強に用いられる金属製のスプリング状のインサートを指します。正式名称は「スプリュー」ですが、日本では「ヘリサート」という商品名が通称として広く浸透しています。母材のねじ穴にヘリサートを挿入することで新たなねじ山を形成し、強度や耐久性を向上させる役割があります。特にアルミニウムやマグネシウムなどの軟質材料において、ねじの締結力を高めたり、ねじ山の損傷を修復したりするために活用されています。
ヘリサートとは何か
ヘリサートとは、コイル状の金属インサートをねじ穴に挿入し、ねじの強度や耐久性を向上させる部品のことです。主にアルミニウム、マグネシウム合金、樹脂などの低強度材料に使用され、オーバーロックによるねじ山の損傷を防ぎます。また、破損したねじ山の補修にも活用可能です。断面が菱形のステンレス製ワイヤーを螺旋状に巻いた構造が特徴で、インサートの外周は母材側のねじ山に、内周は挿入されるボルト側のねじ山に対応しており、元からねじ山があったかのような状態を再現します。これにより、何度もボルトを着脱する場面でも、母材のねじ山を傷めることなく長期間使用できるようになります。
ヘリサートを使用する利点
ヘリサートを使用する最大の利点は、柔らかい素材のめねじの強度を大幅に向上させ、繰り返し使用できる点にあります。アルミや樹脂などの材料は、そのままではねじの締め付けや取り外しを繰り返すことでねじ山が摩耗したり、潰れたりするリスクが高いです。しかし、ヘリサートを挿入することで、ねじ山にかかる力が均一に分散され、高い締結力を維持することができます。これにより、ボルトの抜き差しによる摩耗を抑制し、製品の寿命を延ばすことが可能です。また、ヘリサートは耐振動性や耐摩耗性にも優れており、振動や衝撃によるねじの緩みを防ぐ効果も期待できます。さらに、ねじ穴が破損してしまった場合でも、ヘリサートを用いることで簡単にねじ穴を再生し、部品を再利用できるため、補修にかかるコストや時間を削減することができます。これにより、生産性向上にもつながります。複雑な形状の製品や、ロックワッシャーやナットを取り付けるのが難しい場所でも、ヘリサートロックインサートを使用することで、確実なゆるみ止めが可能です。
ヘリサートの用途
ヘリサートは、その優れた特性から幅広い分野で利用されています。主な用途としては、まず柔らかい材料のねじ穴補強が挙げられます。特にアルミニウムやマグネシウム合金、各種樹脂(POM、アクリル、MCナイロンなど)といった素材は、直接ねじを切ると強度が不足しがちです。このような場合にヘリサートを挿入することで、高い締結力を確保し、ねじの破損を防ぎます。次に、損傷したねじ穴の補修です。既にねじ穴が潰れてしまったり、摩耗してしまったりした箇所でも、ヘリサートを使用することで、元のねじ穴と同じ径とピッチのめねじを再生し、再利用が可能となります。これにより、部品交換の必要がなくなり、修理コストの削減に貢献します。具体的な使用例としては、自動車や航空機のアルミ部品、精密機器や電子機器の筐体、医療機器、金型関連部品などが挙げられます。これらの分野では、軽量化や高精度が求められる一方で、ねじの締結部の信頼性が極めて重要となるため、ヘリサートが広く採用されています。また、JISやISO、UNC/UNFなど、さまざまなねじ規格に対応した製品がラインナップされており、用途に合わせて最適なタイプを選定できる点も大きな特徴です。このように、ヘリサートは、製品の信頼性向上、寿命延長、そしてコスト削減に貢献する重要な部品です。
ヘリサートの種類
ヘリサートには、その用途や特性に応じていくつかの種類が存在します。主なものとして、タング付きヘリサート、タングレスヘリサート、そしてロックタイプヘリサートが挙げられます。それぞれの種類は、挿入方法や機能、適した使用場面が異なります。例えば、タングの有無は作業効率に影響を与え、ロック機能は締結部の緩み防止に効果を発揮します。また、ヘリサートはJISやISO規格だけでなく、ユニファイねじ(UNC/UNF)など、様々なねじ規格に対応した製品が提供されており、用途に応じた選択が可能です。
タング付きヘリサート
タング付きヘリサートは、ヘリサートの先端に「タング」と呼ばれる突起が付いているタイプのものです。このタングは、ヘリサートを挿入する際に専用工具の先端の溝に引っ掛けて、コイルを回しながらねじ穴に挿入するために使用されます。通し穴に挿入する場合は、ヘリサートの挿入が完了した後に、タングを折り取る作業が必要になります。このタングを折り取る作業は、タング折り工具を使って行いますが、折ったタングを回収する手間が発生することがあります。しかし、止まり穴でボルトがタングに当たらない場合や、タングが機能に影響しない場合は、タングを折り取る必要はありません。タング付きヘリサートは、最も一般的なヘリサートの種類として広く普及しており、様々なねじの補強や補修に用いられています。挿入後にタングを折り取る必要があるため、作業工数が増えるというデメリットもありますが、挿入の確実性が高いというメリットもあります。
タングレスヘリサート
タングレスヘリサートは、その名の通り、タング(挿入用の突起)が付いていないタイプのヘリサートです。タングがないため、挿入後のタング折り取りや回収作業が不要となり、作業時間の短縮と効率化が実現します。挿入には、専用工具の溝にノッチと呼ばれる切り欠き部分を引っ掛けて、回しながらねじ込みます。挿入方向は上下どちらからでも可能で、作業の自由度が高いのも特徴です。タングレスヘリサートは、タング付きヘリサートに比べて挿入作業が容易であり、特に量産品への適用や、タングの回収が困難な場所での使用に適しています。ねじ穴の補強や補修といった基本的な機能はタング付きヘリサートと同様に提供され、高い締結力を維持し、ねじの信頼性を向上させます。
ロックタイプヘリサート
ロックタイプヘリサートは、ねじの緩みを防止する機能を備えた特殊なヘリサートです。一般的なヘリサートが円形に巻かれているのに対し、ロックタイプヘリサートは、コイルの内径の一部が円形ではなく、多角形に形成されているのが特徴です。この多角形の部分がボルトの側面を締め付けることで、強い摩擦力を生み出し、緩みにくさを向上させます。特に、温度変化や振動、衝撃によってねじが緩むリスクがある場所での使用に効果的です。自動車部品や航空機、精密機器など、高い信頼性が求められる分野で活用されます。また、調整ねじやセットねじのロック用としても使用され、確実な締結を可能にします。ロックタイプヘリサートを挿入する際には、ロックタイプ専用の工具を使用する必要があります。多角形の形状や深さ、コイル数などは、めねじの規格によって異なるため、適切な製品を選定することが重要です。これにより、ねじの抜けや脱落といった問題を効果的に防ぎ、製品全体の安全性を高めることに貢献します。
ヘリサートの加工方法
ヘリサートの加工は、専用の工具と手順を要する作業です。正確な使い方を習得することで、めねじの強度を確実に向上させることができます。基本的な加工手順は、下穴加工、ヘリサート挿入用のめねじ切り、ヘリサートのねじ込み挿入、そしてタング折り取り(タング付きの場合)の4ステップです。これらの工程を適切に行うことで、ヘリサートの効果を最大限に引き出すことができます。
下穴加工の重要性
ヘリサートを挿入する際の最初のステップであり、最も重要な工程の一つが下穴加工です。下穴とは、ヘリサート用のめねじを切る前に母材に開ける穴のことで、その精度がヘリサートの性能に大きく影響します。下穴の径が適切でないと、その後のタップ加工が正しく行われず、ヘリサートが傾いて挿入されたり、しっかりと固定されなかったりする原因となります。そのため、できる限り真円度の高いドリルやリーマ加工を用いることが望ましいとされています。また、下穴の深さも重要です。ヘリサートの長さだけでなく、タングを折り取るスペースも考慮して、十分な深さを確保する必要があります。一般的に、ヘリサートを挿入するねじのサイズに適応するドリル径を選定し、正確な寸法で下穴を開けることが求められます。メートルねじ用の下穴とは異なる専用の寸法が必要となるため、ヘリサートメーカーが提供する下穴径の推奨表などを参照し、適切なドリル径と深さで加工を行うことが、高品質なヘリサート加工の鍵となります。
ヘリサートの挿入手順
ヘリサートの挿入は、正確な使い方を理解し、専用工具を用いて慎重に行う必要があります。まず、事前に開けた下穴に、ヘリサート専用のタップを使ってねじ山を切削します。このタップは通常のメートルねじ用とは形状やピッチが異なるため、代用はできません。次に、ヘリサートを挿入する前に、下穴の寸法が適切であることを確認します。挿入工具を使用して、ヘリサートをゆっくりと下穴のめねじに沿ってねじ込んでいきます。この際、焦らず丁寧に作業を進めることが重要です。タング付きヘリサートの場合は、タングと呼ばれる突起を工具の溝に引っ掛け、回しながら挿入します。通し穴の場合は、挿入後にタング折り取り工具を挿入し、タングを折り取る作業が必要です。一度挿入したヘリサートは、原則として引き抜けないため、挿入ミスがないよう注意が必要です。タングレスヘリサートの場合は、挿入後のタング折り取り作業が不要なため、作業工数を削減できます。いずれのタイプも、手作業での加工となるため、ある程度の加工技術と時間を要することを認識しておく必要があります。適切な工具と手順で挿入することで、ヘリサートは本来の性能を発揮し、強固なねじ締結を実現します。
ヘリサートの長さと巻き数
ヘリサートの長さは、適用するねじの呼び径(D)を基準として表され、一般的には1倍(1D)、1.5倍(1.5D)、2倍(2D)の3種類が標準品として広く流通しています。一部では2.5倍(2.5D)や3.5倍(3.5D)といったさらに長いものもラインナップされています。この「D」は、ヘリサートタップの穴に挿入した際のヘリサートの全長を示しています。例えば、M6のねじに対して1Dのヘリサートを使用する場合、その長さは約6mmとなります。ただし、ヘリサート自体の長さは呼び寸法と異なり、実際には少し短くなることがあります。例えば、M6(ピッチ1)で1Dの場合、規格で定められた自由巻き数は4.25巻きで、ヘリサート自体の長さは約4.25mmです。ヘリサートを選定する際には、挿入する母材の板厚よりも短いものを選ぶことが重要です。これにより、ヘリサートが母材からはみ出したり、不必要な応力がかかったりすることを防ぎます。また、ヘリサートの自由巻き数は、ヘリサートが自由に巻かれている状態でのコイルの巻き数を指し、ノッチの位置を基準に数えられます。適切な長さと巻き数のヘリサートを選択することで、ねじの締結強度を最大限に引き出し、製品の信頼性を高めることができます。