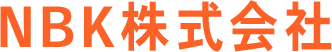アルミ加工は難しい?主な種類と方法、切削の注意点を解説
アルミの加工は、軽量で錆びにくいといった利点がある一方で、素材の特性から難しい側面も持ち合わせています。
この記事では、アルミ加工の代表的な種類と方法を網羅的に解説し、特に難しいとされる切削に焦点を当てます。
加工時に発生しやすい問題とその原因、具体的な対策となる注意点までを詳しく説明することで、品質の高いアルミ製品の製造を支援します。
アルミとは?軽量で加工しやすい金属の基本的な特性
アルミは、鉄やステンレスといった他の金属素材と比較して非常に軽量であることが最大の特徴です。
比重は鉄の約3分の1でありながら、強度を確保できるため、製品の軽量化に貢献します。
また、加工性や熱伝導性、電気伝導性に優れ、リサイクルも容易です。
表面に酸化皮膜を形成するため耐食性が高く、錆びにくい性質も持っています。
これらの特性から、輸送機器から日用品まで幅広い分野で活用されています。
アルミ部品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
アルミ加工の代表的な種類と方法
アルミの加工には、求める形状や用途に応じて様々な種類と方法が存在します。
専用の機械を用いて材料を削る切削加工や、板材を曲げる加工、部品を接合する溶接などが代表的です。
さらに、表面を滑らかにする研磨や、滑り止めのために凹凸をつけるローレット加工、端面を整えるトリマー加工といった仕上げ処理も行われます。
これらの方法を組み合わせることで、複雑な形状の部品も製作可能です。
金属を削り出して成形する「切削加工」
切削加工は、ドリルやエンドミルといった工具を用いて金属材料を削り取り、目的の形状に成形する代表的な加工方法です。
主に、固定した材料に対して回転する工具を当てるフライス加工と、材料自体を回転させて固定した工具で削る旋盤加工に大別されます。
一般的には、まず荒加工で大まかな形状を作り出し、その後、仕上げ加工で寸法精度や表面の滑らかさを高めていきます。
複雑な三次元形状の製作も可能で、高い精度が求められる部品製造において広く採用されている技術です。
用途に合わせて切り分ける「切断加工」
切断加工は、アルミの板材や棒材などを指定された寸法に切り分ける工程です。
加工方法には複数の種類があり、材料の厚みや求められる精度によって使い分けられます。
例えば、厚い材料にはのこ盤やバンドソーが用いられ、薄板の直線切断にはシャーリングが適しています。
より精密な切断や複雑な曲線加工が求められる場合は、熱影響の少ないレーザー加工やウォータージェット加工が選択されます。
手作業で簡易的に切断する際には、専用のカッターが使用されることもあります。
板材をV字やL字に折り曲げる「曲げ加工」
曲げ加工は、アルミの板材をプレスブレーキと呼ばれる機械で挟み込み、圧力をかけて任意の角度に折り曲げる塑性加工の一種です。
主にパンチ(上型)とダイ(下型)という金型を用いて行われ、これらの形状を変えることでL字やV字、箱型など多彩な形状を生み出せます。
アルミは比較的柔らかく延性があるため、曲げ加工に適した素材ですが、力を解放した際に元の形状に戻ろうとする「スプリングバック」という現象が発生しやすい特性があります。
そのため、目的の角度に仕上げるには、この現象を考慮した精密な角度設定が必要です。
部品やネジを通すための「穴あけ加工」
穴あけ加工は、ドリルなどの切削工具を用いてアルミ材に穴をあける基本的な加工です。
ボルトや部品を通すための単純な穴だけでなく、ねじを締結するための雌ねじを形成するタップ加工もこの加工に含まれます。
タップ加工では、下穴をあけた後、タップと呼ばれる工具でねじ山を切っていきます。
また、より高い寸法精度や滑らかな内面が求められる穴に対しては、リーマという工具を用いて内面を精密に仕上げるリーマ加工が行われます。
これらは部品の組み立てにおいて不可欠な工程です。
パーツ同士を熱で接合する「溶接加工」
溶接加工は、2つ以上のアルミ部材の接合部分を熱で溶かし、一体化させる加工方法です。
アルミの溶接では、不活性ガスを用いて溶融部分を大気から保護するTIG溶接やMIG溶接が一般的に用いられます。
アルミは熱伝導率が非常に高いため、熱がすぐに拡散してしまい溶融池の形成が難しく、また融点が低いため溶け落ちやすいという課題があります。
さらに、表面の強固な酸化皮膜を除去しながら作業する必要があり、高品質な溶接を行うには専門的な知識と高度な技術が要求されます。
表面の耐食性と硬度を高める「アルマイト処理」
アルマイト処理は、アルミの表面に陽極酸化皮膜を人工的に生成させる表面処理技術です。
アルミを電解液中で陽極として通電させることで、耐食性や耐摩耗性を大幅に向上させます。
自然にできる酸化皮膜よりもはるかに厚く強固な皮膜を形成するため、傷がつきにくくなり製品の寿命を延ばす効果があります。
また、この皮膜には微細な孔が無数にあり、そこに染料を吸着させることで、シルバーだけでなく黒や金、青といった多彩なカラーリングが可能です。
装飾目的や識別目的で広く利用されています。
なぜアルミ加工は難しいと言われるのか?2つの主な理由
アルミは柔らかく加工しやすい金属とされますが、その特性が逆に加工を難しくする要因ともなります。
素材が柔らかいために傷がつきやすく、切削時にはバリや構成刃先が発生しやすい傾向があります。
また、熱伝導率の高さと熱膨張率の大きさから、加工熱による伸びや歪みといった寸法変化も起こり得ます。
これらの問題を回避し、高精度な加工を実現するには、アルミの特性を深く理解した上で適切な対策を講じる必要があります。
熱伝導率の高さによる溶着や変形
アルミは熱伝導率が非常に高いため、切削などの加工時に発生した熱が工具や材料に素早く伝わります。
この熱によってアルミ材が膨張し、加工中と冷却後で寸法に差異が生じる熱変形が起こりやすくなります。
また、切削工具の刃先と切りくずが高温・高圧で接触することで、切りくずの一部が刃先に溶着してしまう「構成刃先」という現象もアルミ加工特有の課題です。
構成刃先が成長と脱落を繰り返すと、加工面のむしれや寸法精度の低下を引き起こすだけでなく、工具の寿命を縮める原因にもなります。
そのため、加工中の温度上昇をいかに抑えるかが重要です。
素材の柔らかさに起因する精度の出しにくさ
アルミは素材として柔らかいため、切削時の抵抗が少なく加工自体は容易に感じられます。
しかし、この柔らかさが原因で、加工時に工具から受ける圧力によって材料がたわみやすく、寸法精度を出すのが難しくなります。
特に薄肉の部品や長い材料を加工する際には、びびり振動が発生し、加工面の悪化や寸法誤差につながることがあります。
また、加工のために材料を固定する際、クランプの力が強すぎると素材が変形したり、打痕が残ったりするリスクも考慮しなければなりません。
高い精度を維持するには、これらの変形要因を排除する工夫が必要です。
アルミの切削加工を成功させるための4つのポイント
アルミ切削の難しさを克服し、高精度な加工を実現するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これらは工具の選定から切削条件の設定、冷却方法に至るまで多岐にわたります。
加工中の素材を確実に固定する治具の工夫も欠かせません。
これから紹介する4つのポイントを実際に試してみて、自身の加工環境に最適な条件を見つけ出すことが、品質向上への近道となります。
すくい角の大きいアルミ専用の工具を選ぶ
アルミの切削加工では、工具の選定が品質を大きく左右します。
アルミは柔らかく粘り気があるため、切りくずがスムーズに排出されるように設計された刃物が必要です。
具体的には、刃先のすくい角が大きく、切れ味の良いアルミ専用の工具を使用することが原則です。
フライス盤で用いるエンドミルや旋盤加工で使うチップには、こうしたアルミ向けの製品が用意されています。
工具の材質は、靭性に優れるハイス(高速度鋼)や、耐摩耗性が高い超硬、サーメットなどがあり、加工内容やコストに応じて選択します。
特に大量の切りくずを排出する荒加工では、ラフィングエンドミルが効果的です。
溶着を防ぐために切削速度を高速に保つ
アルミ加工で問題となる構成刃先の発生を防ぐためには、切削速度を適切に設定することが効果的です。
切削速度が低いと、工具の刃先と切りくずが接触している時間が長くなり、摩擦熱によって溶着が起こりやすくなります。これを防ぐには、切削速度をできるだけ高速に保つことが有効です。
速度を上げることで、切りくずが熱を持つ前に素早く加工点から離れるため、刃先への溶着を抑制できます。ただし、むやみに速度を上げると機械や工具に過大な負荷がかかり、びびり振動の原因となる場合もあります。
使用する機械の剛性や工具の性能を考慮し、バランスの取れた切削速度を見つけることが求められます。
適切なクーラントを使用して摩擦熱を抑える
加工時に発生する熱を効果的に除去し、溶着や熱変形を防ぐためには、クーラント(切削油)の使用が不可欠です。
クーラントには、加工点を冷却して温度上昇を抑える冷却作用と、工具と材料の間の摩擦を減らす潤滑作用があります。これにより、構成刃先の発生を抑制し、加工面の品質を向上させると同時に、工具の摩耗を抑えて寿命を延ばす効果も期待できます。
アルミ加工で用いられる切削油には、水で希釈して使用する水溶性と、原液のまま使用する油性のタイプが存在します。一般的には、冷却効果の高い水溶性のクーラントが広く選択される傾向にあります。
合金の種類に合わせた最適な切削条件を設定する
アルミと一括りに言っても、添加される元素によって特性が異なる様々な合金が存在し、その種類によって加工性も大きく変わります。
例えば、純アルミに近い1000系は非常に柔らかく粘りがあるため溶着しやすい一方、ジュラルミンと呼ばれる2000系や7000系は硬度が高く、比較的切りくずが処理しやすい特性を持ちます。
したがって、加工するアルミ合金の種類に応じて、切削速度、一刃当たりの送り量、切り込み深さといった切削条件を適切に設定することが求められます。
工具メーカーが提供する推奨値を基準としながら、実際の加工で発生する切りくずの状態や加工面の品質を確認し、微調整していく作業が必要です。
【用途別】知っておきたいアルミ合金の種類と特徴
アルミニウムは、他の元素を添加して合金にすることで、強度や耐食性といった特性を大きく向上させることができます。
これらのアルミ合金は、添加された主な元素によって1000系から7000系まで分類されており、それぞれ異なる特徴を持ちます。
スマートフォンのケースのような精密部品から、航空機や鉄道車両などの大型構造物まで、用途に応じて最適な合金が選定されます。
ここでは代表的な系統の特徴と主な用途を紹介します。
純度が高く加工性に優れる「1000系(純アルミ系)」
1000系は、アルミニウム純度が99.00%以上の純アルミ系の合金です。
不純物が少ないため、素材自体が非常に柔らかく、塑性加工性に優れています。
また、電気伝導性や熱伝導性が高く、耐食性も良好です。
身近な例では1円硬貨がこの系統のアルミで作られています。
これらの特性から、電線などの導電材、照明器具の反射板、各種容器、ネームプレートなどに利用されます。
ただし、強度は他の合金系と比較して低いため、構造材料には向きません。
切削加工においては、その柔らかさと粘りから工具への溶着が起きやすく、構成刃先の発生に特に注意が必要です。
銅を含み高い強度を持つ「2000系(Al-Cu系)」
2000系は、主として銅(Cu)を添加した合金で、ジュラルミンや超ジュラルミンとして広く知られています。
熱処理を施すことで、アルミ合金の中でも特に高い強度を発揮し、種類によっては鋼材に匹敵するほどの強度を持つものもあります。
この優れた強度と軽量性を活かし、航空機の機体構造材、いわば機体を覆う服のような役割を担う部品に多く採用されています。
一方で、銅を含むため耐食性が低いという欠点があり、使用環境によっては表面に防食処理を施す必要があります。
溶接性もあまり良くないため、接合にはリベットなどが用いられることが多いです。
マンガンを加え耐食性を高めた「3000系(Al-Mn系)」
3000系は、マンガンを添加元素とする合金で、純アルミが持つ良好な加工性や耐食性を損なうことなく、強度を向上させているのが特徴です。
非熱処理型の合金であるため、複雑な形状への成形加工にも適しています。
このバランスの取れた性質から、非常に幅広い用途で利用されており、代表的な例として飲料用のアルミ缶のボディ部分が挙げられます。
その他にも、カラーアルミとして屋根材や外壁材、調理器具、各種容器など、私たちの生活に身近な製品に多く使われています。
汎用性が高く市場に広く流通しているため、小ロットでのオーダーにも対応しやすい材料の一つです。
シリコン添加で耐摩耗性に優れる「4000系(Al-Si系)」
4000系は、シリコン(Si)を主な添加元素とするアルミ合金です。
シリコンを添加することにより、融点が低くなるため、溶接時の溶加材(フィラーメタル)として広く利用されています。
また、耐摩耗性や耐熱性に優れ、熱膨張率が低いという特徴も持っています。
この性質を活かして、自動車やバイクのエンジン内部で使われるピストンやシリンダーヘッドといった、高温・高摩擦環境に晒される部品の材料としても重要です。
鋳造性も良好なため、複雑な形状の鋳物部品にも適しています。
用途が比較的専門的なため、材料の価格や加工にかかる費用は、他の汎用的な合金とは異なる場合があります。
耐食性と溶接性が良い「5000系(Al-Mg系)」
5000系は、マグネシウム(Mg)を主な添加元素とする合金です。
非熱処理型合金の中では最も強度が高いグループに属し、特に耐食性に優れています。
海水や工業地帯の汚染された空気に対しても強い抵抗力を示すため、船舶の部材、自動車のホイール、沿岸地域の建築外装材、さらには溶接構造物や圧力容器など、過酷な環境下で使用される製品に広く採用されています。
また、溶接性も良好で、溶接後も強度低下が少ないという利点があります。
これらの扱いやすさから、DIYなどの場面で個人がアルミ加工を行う際にもよく選ばれる材料の一つです。
強度・耐食性・加工性のバランスが良い「6000系(Al-Mg-Si系)」
6000系はマグネシウムとシリコンを添加した合金で、強度、耐食性、加工性のバランスに優れているのが最大の特徴です。
代表的な材質であるA6063は押出加工性に非常に優れており、住宅用のサッシやドア、フェンスといった建築用形材として広く普及しています。
一方、A6061はA6063よりも高い強度を持ち、機械部品や車両の構造材などに用いられます。熱処理によって強度を調整でき、溶接性も良好なため、設計の自由度が高いことも利点です。
この汎用性の高さから、6000系はアルミ合金の中でも特に使用量が多い系統となっています。
アルミ合金で最高の強度を誇る「7000系(Al-Zn-Mg系)」
7000系は、亜鉛とマグネシウムを主な添加元素とする合金で、熱処理を施すことでアルミ合金の中で最高の強度を発揮します。
代表的なA7075は「超々ジュラルミン」とも呼ばれ、その卓越した強度と軽量性を活かして、航空機の主翼や胴体といった主要構造部品に不可欠な材料です。
また、競技用の自転車フレームやスキーのストック、野球のバットなど、高い性能が求められるスポーツ・レジャー用品にも採用されています。
一方で、非常に高い強度を持つ反面、応力腐食割れへの感受性が高く、設計や使用環境には注意が求められます。
まとめ
アルミ加工は素材の特性上、熱や変形への対策が重要であり、適切な工具選定と切削条件の設定が品質を左右します。また、製品の用途に応じて最適なアルミ合金を選ぶ知識も不可欠です。
もし自社での加工が難しい場合や、より専門的な技術が必要な場合は、信頼できる加工業者へ依頼することを検討します。加工を専門とする企業やメーカーは、豊富な経験と設備を持っています。例えば大阪のような工業地帯には多くの専門会社が存在します。
複数の業者から見積もりを取り、加工費だけでなく、技術力や実績を比較検討することで、要望に適したパートナーを見つけることができます。
アルミ部品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!