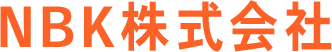同軸度とは?同心度との違い、幾何公差の記号や測定方法を解説
同軸度とは、2つの円筒の中心軸がどれだけ一直線上からズレているかを示す幾何公差の一種です。
設計や品質管理の現場では、部品の性能を保証するために正確な理解が求められます。
この記事では、同軸度の基本的な定義から、混同されやすい同心度との違い、図面で使われる記号の意味、そして具体的な測定方法までを網羅的に解説します。
同軸度とは?2つの円筒の中心軸のズレを示す幾何公差
同軸度は、基準となる円筒の中心線(データム軸線)に対して、もう一方の円筒の中心線がどれだけズレているかを規制する幾何公差です。
この定義が示す意味は、2つの軸が空間的にどれだけ一直線上に並んでいるかということであり、軸の傾きや位置のズレ(偏心)を総合的に評価します。
例えば、モーターのシャフトのように、複数の径を持つ部品が高速で回転する場合、各部分の軸が一致していないと振動や騒音、摩耗の原因となります。
そのため、同軸度は回転体のバランスや嵌め合い部品の精度を確保する上で非常に重要な項目です。
同軸度と比較される「同心度」との違いを解説
同軸度と同心度は、どちらも中心のズレを規制する幾何公差であるため、しばしば混同されます。
しかし、この2つは評価の対象が根本的に異なります。
評価対象が「軸全体」か「円の中心点」か
同軸度と同心度の最も大きな違いは、評価対象の次元性にあります。
同軸度が規制するのは、対象となる円筒の「軸線全体」です。
この軸線が、データム軸線を中心とする指定された直径の円筒空間内に収まっているかを評価します。
一方、同心度が規制するのは、対象となる円の「中心点」です。
データム円の中心点から、対象となる円の中心点までの距離が、指定された直径の円の範囲内にあるかを評価します。
このように、同軸度は立体的な軸のズレを規制するのに対し、同心度は特定の平面上における点のズレを規制する点で異なります。
これは位置度公差の考え方に近いもので、同軸度の方がより厳格な規制といえます。
同軸度の図面への指示方法と記号の読み取り方
設計者が意図した製品精度を実現するためには、JISなどの製図規格に準拠した方法で、図面に公差を正しく指示する必要があります。
同軸度の表記も例外ではなく、定められた様式に従って公差情報や基準となるデータムを明確に記入しなければなりません。
ここでは、同軸度を図面へ指示する際の具体的な表記方法と、その記号が何を意味するのか、正確な読み取り方について解説します。
これにより、設計者と加工者、検査者の間で認識の齟齬が生まれるのを防ぎます。
同軸度を表す幾何公差記号
同軸度を示す幾何公差記号は、二重丸(◎)です。この記号は、2つの円が完全に中心を共有している状態を模式的に表しています。
図面への指示は、公差記入枠を用いて行います。まず、矢印で規制したい形体(円筒)を示し、そこから引き出し線で公差記入枠につなげます。枠内は通常3つに区切られ、左の区画に同軸度の記号「◎」を、中央の区画に公差値を、右の区画に基準となるデータム軸線を示すアルファベットを記入します。
円周振れや全振れも回転体の精度を示す幾何公差ですが、これらは部品を回転させた際の表面のブレを規制するものであり、軸そのもののズレを規制する同軸度とは定義が異なります。
公差域の考え方【直径〇〇の円筒内】
同軸度の公差値は、規制対象となる軸線が存在できる空間的な範囲を指定します。
この公差域の考え方は、データム軸線を中心軸とする仮想的な円筒で定義されます。
図面で公差値の前に直径記号「φ」が付いているのは、この公差域が円筒状であることを示すためです。
例えば、図面に「◎φ0.1A」と指示されている場合、データム軸線Aを中心とする直径0.1mmの円筒の中に、対象となる軸線の全体が収まっている必要がある、ということを意味します。
この数値の大きさは製品に求められる機能や性能に応じて設定され、高精度な部品では0.05や0.03といった厳しい値が要求されることもあります。
独立の原則(記号Ⓢ)と最大実体公差(MMC)の適用
幾何公差とサイズ公差(寸法公差)の関係には、原則として「独立の原則」が適用されます。
これは、寸法と形状がそれぞれ独立して公差を満足しなければならないという考え方です。
特別な指示がない限り、この原則に従います。
しかし、部品同士のはめ合いなどを考慮する場合、「最大実体公差(MMC)」を適用することがあります。
MMC(記号Ⓜ)を指示すると、部品の寸法が最も材料体積が大きくなる状態(軸なら最大径)から外れるほど、幾何公差の値に追加の公差(ボーナス公差)が許容されます。
この設定により、機能性を損なわずに部品の合格範囲を広げ、コストダウンを図ることが可能になります。
この考え方は平行度や角度といった他の幾何公差にも適用されます。
NBKでは検査のみのご依頼も承っております!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
同軸度の代表的な測定方法3選
図面に指示された同軸度を保証するためには、製品がその精度を満たしているかを確認する検査工程が不可欠です。
同軸度の測定方法は一つではなく、要求される精度や対象物の大きさ、生産量、保有設備などによって適切な手法を選択する必要があります。
代表的な同軸度の測定方法を知ることで、品質管理のレベルを高められます。
ここでは、現場でよく用いられる3つの計測手法を取り上げ、それぞれの特徴や注意点を解説し、適切な検査方法の選択に役立つ情報を提供します。
Vブロックとダイヤルゲージで測定する方法
Vブロックとダイヤルゲージを用いた測定は、比較的簡易的な同軸度の確認方法です。
まず、測定対象物の基準となる円筒部分をVブロックに乗せ、測定したい部分にダイヤルゲージなどの測定器の測定子を当てます。
次に対象物を手でゆっくりと1回転させ、その間のダイヤルゲージの指針の振れの最大値と最小値を読み取ります。
この振れの幅(全振れ量)の半分が、軸の偏心量に相当し、同軸度の近似値として扱われます。
ただし、この方法は対象物自体の真円度が低いと、その形状誤差も測定値に含まれてしまい、正確な同軸度を評価できないという欠点を持つ手法です。
三次元測定機で高精度に測定する方法
三次元測定機を用いた測定は、同軸度を非常に高精度に評価できる方法です。
この測定機は、プローブと呼ばれる先端球で対象物の表面に接触し、その点の三次元座標を精密に取得します。
同軸度の測定では、まず基準となるデータム円筒上の複数点を測定し、その座標データから空間的なデータム軸線を算出します。
続いて、評価対象の円筒部分も同様に測定し、その中心軸線を算出します。
最後に、三次元測定ソフトウェアが、これら2つの軸線が空間的にどれだけズレているかを計算し、同軸度として評価結果を出力します。
この方法は、対象物の形状誤差の影響を受けにくく、信頼性の高い測定が可能です。
真円度測定機・画像測定器で測定する方法
真円度測定機は、対象物を精密なテーブル上で回転させながら、検出器で半径方向の変位を測定する装置であり、同軸度の高精度な測定にも利用されます。
この装置では、基準となる断面と評価対象となる断面のそれぞれの中心点を算出し、その中心点のズレを同軸度として評価できます。
真円度や円筒度も同時に測定できるため、精密な機械加工部品の評価に適しています。
また、非接触で測定を行う画像測定器も有効な手段です。カメラで捉えた対象物の輪郭から、ソフトウェアが各円筒の中心軸を算出し、そのズレを計算します。
キーエンスなどが提供する高性能な画像測定器は、小物部品や変形しやすい部品の加工後の検査で力を発揮します。
まとめ
同軸度は、2つの円筒部分の軸が持つズレを規制する幾何公差で、特に回転する部品の性能を保証する上で重要な役割を果たします。
一般的に混同されやすい同心度が2次元的な中心点のズレを評価するのに対し、同軸度は3次元的な軸全体のズレを評価するという明確な違いがあります。
図面では二重丸の記号で指示され、その公差域はデータム軸を中心とする円筒領域で定義されます。
測定方法としては、Vブロックとダイヤルゲージを用いた簡易的な確認から、三次元測定機や真円度測定機、画像測定器を用いた高精度な評価まで、要求される品質レベルに応じて使い分けられます。
例えば、モーターのシャフトのような部品では、正確な同軸度の管理が振動や異音の防止に直結するため、設計段階での適切な指示と製造・検査段階での確実な測定が不可欠です。
NBKでは検査のみのご依頼も承っております!是非ご相談ください。
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら