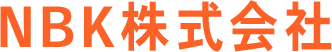製缶加工とは?板金加工との違いや加工手順をわかりやすく解説
製缶加工とは、主に厚い金属板を切断、曲げ、溶接などの手法を用いて、立体的な製品へと作り上げる金属加工技術です。
タンクや鉄骨、産業機械の架台といった大型の構造物を製作する際に用いられます。
本記事では、製缶加工の基礎知識から、混同されがちな板金加工との違い、そして実際の加工手順について詳しく解説します。
これから製缶加工の依頼を検討している担当者の方が、発注前に知っておくべき情報を網羅的に紹介します。
製缶加工の基本を解説
製缶加工とは、金属板や形鋼、パイプなどの材料に切断や曲げ、溶接といった加工を施し、立体的な製品を製造する技術全般を指します。
一般的に「鉄工」とも呼ばれ、主に厚みのある鋼板を用いてタンクや水槽、機械の架台といった大型の構造物を製作する際に用いられるのが特徴です。
板金加工としばしば比較されますが、扱う材料の厚さや製品の大きさ、求められる精度において明確な違いが存在します。
製缶加工は厚い金属板を立体的な製品にする技術
製缶加工の最も大きな特徴は、比較的厚い金属板(厚板)を主材料として扱う点にあります。
この厚板を図面に基づいて切断し、プレス機で曲げたり、ロールベンダーと呼ばれる機械で円筒形に丸めたりします。
その後、加工された複数の部品を溶接によって接合し、一つの立体的な製品として組み立てていきます。
この一連の工程を経て、貯蔵用のタンクや建物の鉄骨、産業機械の土台となる架台など、強度と耐久性が求められる大型の構造物が作られます。
材料の切断から組み立て、仕上げまで、幅広い技術を駆使して製品を形にするのが製缶加工です。
製缶加工で作られる製品の具体例
製缶加工によって製造される製品は、私たちの身の回りや産業の現場で幅広く利用されています。
代表的な例としては、液体や気体を貯蔵するためのタンクや水槽、プラント設備で使われる配管やダクトなどが挙げられます。
また、工作機械や産業用ロボットの土台となる頑丈な架台やフレームの製作も、製缶加工の得意分野です。
その他にも、建築現場で用いられる鉄骨の部材や、橋梁の一部、船体のブロックなど、大型で高い強度が要求される構造物の多くがこの技術によって生み出されています。
このように、社会インフラやものづくりを支える重要な機械・構造物の製造に欠かせない加工方法です。
製缶加工でよく使われる金属材料
製缶加工では、製品の用途や求められる性能に応じて様々な金属材料が使い分けられます。
最も一般的に使用されるのは、加工性に優れコストも比較的安い鉄(SS400など)です。
強度と耐久性が求められる産業機械の架台や建築用の鉄骨など、幅広い製品の材料となります。
また、耐食性が要求される化学プラントのタンクや食品機械の部品には、ステンレス鋼(SUS304など)が頻繁に用いられます。
軽量化が必要な場合にはアルミニウムが選ばれることもあり、その他、耐摩耗性や耐熱性に優れた特殊な鋼材が使用されるケースもあります。
それぞれの金属の特性を理解し、最適な材料を選定することが重要です。
製缶部品でのコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
製缶加工と板金加工の明確な違い
製缶加工と板金加工は、どちらも金属板を加工する技術ですが、その目的や手法には明確な違いがあります。
これらの違いを理解することは、自社が作りたい製品に適した加工方法を選定する上で非常に重要です。
主に「扱う金属板の厚さ」「製造する製品の大きさと用途」「加工に求められる精度」という3つの観点から、両者の差異を把握することで、より適切な業者選定と発注が可能になります。
扱う金属板の厚さが異なる
製缶加工と板金加工を区別する最も分かりやすい基準の一つが、加工対象となる金属板の厚さです。
一般的に、板金加工では薄い金属板(7mm以下)を扱い、製缶加工では厚い金属板(7mm以上)を主に扱うとされていますが、この数値基準は企業や専門業者によって異なります。例えば、板金専門業者では2.0mmまたは1.5mm以下の板厚を扱い、製缶専門業者では3.0mm以上の板厚を主とするところや、6.0mmを境にすることもあるなど、明確な業界統一基準は決まっていません。
この板厚の違いにより、使用する加工機械や技術も大きく異なります。製缶加工では厚板を扱うため、より大きな力が必要なプレス機や切断機が用いられます。また、板金加工に比べて製品の寸法公差は比較的緩やかに設定される傾向があり、ミクロン単位の精度よりも、構造物としての強度や機能性が重視されることが多いです。
製造する製品の大きさと用途が異なる
扱う板厚の違いは製造される製品の大きさと用途に直接的に反映されます。
板金加工では自動車のボディパーツや家電製品の筐体精密機器のカバーといった比較的小型で複雑な形状の部品が主に作られます。
一方製缶加工は厚板を用いるため工場設備用のタンク建物の鉄骨産業機械の頑丈な架台など大型で強度を要する構造物の製造を得意とします。
製品を発注したい会社やメーカーは自社が求める製品のサイズや使用環境を考慮しどちらの加工技術が適しているかを判断する必要があります。
加工に求められる精度が異なる
加工に求められる精度の基準も、両者を見分ける重要なポイントです。
板金加工は、電子機器の筐体や精密部品など、コンマミリ単位の高い寸法精度が要求される製品を多く扱います。
部品同士の嵌合や緻密な組み立てが必要とされるため、図面に対する忠実性が厳しく問われます。
対照的に、製缶加工で製造されるタンクや架台などの大型構造物では、強度や耐久性、機能性が最優先されることが多く、板金加工ほどの厳しい精度は求められない場合があります。
ただし、機械の土台となるフレームなど、後工程で精密な部品が取り付けられる製品については、製缶加工であっても高い加工精度が必要となるケースも存在します。
製缶加工の基本的な6つの手順
製缶加工は単一の作業ではなく複数の工程を経て製品を完成させます。
まず図面から必要な材料の形状を割り出すマーキング作業から始まり切断曲げ溶接仕上げそして検査という一連の流れで進められます。
各工程には専門的な技術と知識が要求され特に大型の製品になるほど各ステップでの正確な作業が最終的な品質を左右します。
また製品によっては製缶加工の後にさらに精度を高めるための機械加工が施される場合もあります。
STEP1:製作図面の展開とマーキング
製缶加工では、まず図面設計が行われ、その後に材料の切断や成形などの工程へと進みます。支給された製作図面を正確に読み解くことは、これらの工程において非常に重要です。図面には製品の最終的な三次元形状が示されているため、これを平面の金属板からどのように切り出し、曲げるかを計算する「展開」作業が必要です。この展開図に基づき、原寸の鋼板上に切断線や曲げ線、穴あけ位置などを書き込んでいく「けがき」と呼ばれるマーキング作業を行います。このマーキングが製品の寸法精度を決定する基礎となるため、非常に重要な工程です。最近では、CADデータを利用して自動でマーキングを行う機械も導入されています。製缶加工の一般的な工程としては、図面作成、切断・抜き加工、穴あけ・曲げ加工、溶接加工、研磨・表面処理、組み立て、検査などが挙げられます。
STEP2:鋼材の切断・溶断
マーキング作業が完了すると、次はその線に沿って鋼材を必要な形状に切り出す工程に移ります。
切断方法は、材料の厚さや材質、求められる精度によって使い分けられます。
比較的薄い板にはシャーリングマシンという機械で剪断し、厚い板や複雑な形状の切断には、レーザー加工機やプラズマ溶断機、ガス溶断機が用いられます。
特にレーザー加工は、切断面が綺麗で精度が高いという特徴を持ちます。
この切断工程の精度が、後の組み立てや溶接作業の効率と品質に大きく影響するため、図面通りに正確に切り出す技術が求められます。
STEP3:穴あけや曲げ加工で形状を作る
切断された平面の鋼材に、立体的な形状を与えていくのがこの工程です。
代表的な加工として、プレスブレーキという機械を使用して鋼板をV字やL字に折り曲げる曲げ加工があります。
また、ロールベンダーを使えば、鋼板を円筒形やR形状に曲げることが可能です。
ボルトを通すための穴や配管用の開口部を設ける際には、ボール盤やドリル、マシニングセンタなどが用いられます。
これらの加工を組み合わせることで、単純な板材が複雑な形状を持つ部品へと姿を変えていき、最終製品の骨格が形成されます。
STEP4:溶接で各パーツを接合する
形状が作られた複数のパーツを、図面に従って一つに組み立て、接合していくのが溶接工程です。
溶接は、金属を熱で溶かして一体化させる技術であり、製缶加工の中核をなす非常に重要な作業です。
製品の材質や板厚、求められる強度に応じて、アーク溶接、半自動溶接(CO2/MAG溶接)、TIG溶接といった様々な手法が使い分けられます。
溶接部の品質は製品全体の強度と耐久性に直結するため、溶接を行う作業者には高い技術力と豊富な経験が要求されます。
確実な接合を行うことで、頑丈な立体構造物が完成します。
STEP5:歪み取りや表面処理で仕上げる
溶接を行う際、金属は局部的に高温に熱せられた後、冷却される過程で収縮し、製品に歪みや変形が生じることがあります。
この歪みを放置すると、製品の寸法精度が損なわれたり、機能に問題が出たりするため、矯正作業が不可欠です。
歪み取りは、ガスバーナーで加熱したり、ハンマーで叩いたりして形状を整える熟練の技術を要する作業です。
その後、溶接部や表面の凹凸をサンダーなどで滑らかにする研磨作業や、錆を防ぐための塗装といった表面処理を施し、製品の外観と耐久性を高めて完成度を上げます。
STEP6:厳しい検査を経て出荷される
全ての加工工程が完了した後、製品は出荷される前に厳格な検査を受けます。
この最終検査では、まずメジャーやノギスなどを用いて、製品が図面通りの寸法で作られているかを確認します。
外観に傷や打痕がないか、溶接部に割れや溶け込み不足といった欠陥がないかも目視や専用の検査機器でチェックされます。
特に強度や気密性が求められる製品では、超音波探傷検査や放射線透過検査などの非破壊検査が行われることもあります。
品質基準をクリアすることが難しい製品もあり、この厳しい検査に合格した製品だけが、顧客のもとへ出荷されます。
製缶加工ならではのメリット
製缶加工は、プレス加工のように高価な金型を必要としないため、一点ものや小ロットの生産に非常に適しています。
試作品や特注品の製作において、初期投資を抑えながら柔軟に対応できる点は大きな強みです。
また、板厚やサイズ、形状の自由度が高く、数メートルに及ぶような大型のタンクや架台、複雑な構造を持つ装置フレームなど、他の加工方法では製造が困難な製品も作ることが可能です。
高い強度を持つ製品を製作できる点も、産業機械や建築分野で重宝される理由の一つです。
製缶加工で注意すべきデメリット
製缶加工における最大の注意点は、溶接時の熱によって生じる金属の歪みです。
この熱歪みは製品の寸法精度に影響を及ぼすため、コントロールや後工程での矯正作業に高い技術と手間を要します。
そのため、板金加工のようなミクロン単位の精密な寸法を出すことは一般的に困難です。
また、加工工程の多くが作業者の手作業に依存するため、品質が職人の技術力に左右されやすい側面も持ちます。
手作業が中心となることから、一点ものの製作コストは割高になる傾向があり、量産には向いていません。
まとめ
製缶加工は、厚い金属板を用いてタンクや架台といった大型で高強度な立体構造物を製造する技術です。
薄板を扱う板金加工とは、材料の厚さ、製品のサイズ、求められる精度において明確な違いがあります。
加工は図面の展開から始まり、切断、曲げ、溶接、仕上げ、検査という手順で進められ、各工程で専門的な技術が求められます。
小ロット生産や大型製品に対応できるメリットがある一方で、溶接による歪みの発生やコストといった課題も存在します。
これらの特性を理解することが、適切な加工方法を選定する上で重要となります。
製缶部品でのコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら