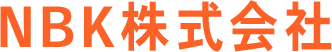切削加工とは?基礎知識から種類、特徴までわかりやすく解説
切削加工は機械部品などを製造する上で欠かせない基本的な技術です。
この記事では切削の基本から具体的な加工方法、メリット・デメリット、さらには品質を高めるための注意点まで、切削加工に関する基礎知識を網羅的に解説します。
製造業に関わる方や機械系の学生が基礎から体系的に理解できるよう分かりやすく説明を進めます。
切削加工とは?不要な部分を取り除いて目的の形を作る加工法
切削加工の定義は、刃物(工具)を用いて材料の不要な部分を削ることで、目的の寸法や形状を作り出す加工方法です。
これは除去加工の一種であり、材料を溶かして固める鋳造や、材料を接合する溶接、表面をわずかに削って滑らかにする研磨とは区別されます。
ドリルで穴を開けたり、ノコギリで木材を切ったりすることも広い意味での切削加工に含まれ、現代の工業製品の多くがこの加工方法によって作られています。
加工品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
切削加工が持つ3つのメリット
切削加工は、現代のものづくりにおいて広く採用されている加工方法であり、多くのメリットが存在します。
その利点として、非常に高い精度で部品を製作できること、金属から樹脂まで多種多様な材料に対応できること、そして金型を必要としないため一個からの試作品製作にも柔軟に対応できることなどが挙げられます。
これらの特徴により、様々な産業分野で重要な役割を担っています。
メリット1:高精度な加工で複雑な形状も実現できる
切削加工の最大のメリットは、高い寸法精度を実現できる点にあります。
NC工作機械を用いれば、μm(マイクロメートル)単位での精密な制御が可能であり、設計通りの形状を正確に作り出せます。
また、表面の滑らかさも特長の一つで、加工面の凹凸を示す表面粗さをRa(算術平均粗さ)といった指標で管理することで、鏡面に近い仕上げも可能です。
この高精度な加工技術により、自由な曲面を含む三次元の複雑な形状も実現できるため、精密機器や航空宇宙分野の部品製造に不可欠です。
メリット2:多種多様な材料に対応可能
切削加工は、幅広い素材に対応できる利点を持っています。
鉄やステンレス、アルミ、チタンといった一般的な金属はもちろん、銅や真鍮、鉛などの非鉄金属、さらには樹脂や木材、石といった非金属材料まで加工可能です。
それぞれの素材の特性に合わせて工具や加工条件を最適化することで、様々な製品を生み出せます。
例えば、自動車のアルミホイールやスマートフォンの金属筐体も、この技術を用いて作られる代表例です。
多岐にわたる素材に対応できる汎用性の高さが、切削加工が多くの産業で利用される理由の一つとなっています。
メリット3:金型が不要で1個からの試作にも向いている
切削加工は、射出成形やプレス加工とは異なり、製品ごとの専用の金型を製作する必要がありません。
設計データをプログラムに入力すれば直接加工を開始できるため、開発段階における1個からの試作や、多品種少量生産に非常に適しています。
金型製作にかかる高額な初期費用や長い製作期間が不要なため、コストを抑えつつ迅速に製品を形にすることが可能です。
また、設計変更が生じた場合でもプログラムを修正するだけで柔軟に対応できるため、製品開発のスピードを大幅に向上させます。
知っておきたい切削加工の2つのデメリット
多くの利点を持つ切削加工ですが、万能というわけではなく、いくつかのデメリットも存在します。
特に、加工に要する時間や、作り出せる形状の制約については事前に理解しておく必要があります。
これらの課題を把握し、適切な技術やコツを用いることで、切削加工の能力を最大限に引き出すことができます。
ここでは、代表的な2つのデメリットについて解説します。
デメリット1:材料の除去に時間がかかり大量生産には不向き
切削加工は、材料の塊から削り取って形を作るため、製品完成に時間がかかります。
複雑な形状や大きな部品は、加工時間が長くなる傾向にあります。
この加工速度の問題から、金型を用いるプレス加工や射出成形と比較して、数千、数万個といった大量生産にはコスト面で不向きです。
削り取られた部分は切りくずとして廃棄されるため、材料の歩留まりが悪くなる点も考慮すべき要素です。
デメリット2:加工形状に制約があり除去できない部分がある
切削加工では、使用する工具の形状や大きさ、工具の動かせる範囲によって、加工できる形状に制約が生じます。
例えば、工具が物理的に届かない部分や、鋭利な内側の角(隅Rなし)を作り出すことはできません。
また、工具の直径よりも細い溝や、工具長に対して極端に深さのある穴なども加工が困難です。
こうした制約があるため、設計段階から切削加工が可能かどうかを考慮に入れる必要があります。
アンダーカットと呼ばれる、工具が直接届かない隠れた部分の加工には、特殊な工具や多軸の加工機が求められます。
代表的な切削加工の種類とそれぞれの特徴
切削加工と一言でいっても、その方法は一つではありません。
材料を回転させるのか、工具を回転させるのかといった動作の違いによって、様々な種類に分類されます。
代表的なものとして、丸い形状を作る旋削加工、平面や溝を加工する方法、そしてドリルによる穴あけ加工などが挙げられます。
作りたい製品の形状に応じて、これらの加工方法を単独または組み合わせて用いるのが一般的です。
回転する材料を削る「旋盤加工」
旋盤加工は、加工する材料を回転させ、そこに固定したバイトと呼ばれる工具を当てることで削る方法です。
チャックという掴み具で材料を固定して高速で回し、バイトを前後左右に動かして表面を削ったり、穴を開けたり、ねじを切ったりします。
この方法の特性上、出来上がる形状は円筒形や円錐形といった回転体のものが中心となります。
主に丸棒状の材料から、シャフトやボルト、フランジといった部品を製作する際に用いられ、旋盤という専用の工作機械が使用されます。
工具を回転させて平面や溝を作る「フライス加工」
フライス加工は、加工する材料をテーブルに固定し、エンドミルや正面フライスといった回転工具を動かして削る加工方法です。
旋盤加工とは逆に、工具側が回転するのが大きな特徴です。
この方法により、材料の平面を削り出したり、溝や段差を作ったり、曲面を加工したりと、非常に多様な形状を生み出せます。
主に四角いブロック状の材料から加工を始めることが多く、機械の筐体やプレート部品など、角物の加工で広く用いられます。
フライス盤やマシニングセンタといった工作機械がこの加工に使用されます。
ドリルで材料に穴を開ける「穴あけ加工」
穴あけ加工は、ドリルと呼ばれる専用の切削工具を回転させながら材料に押し当てて穴を開ける、最も基本的で多用される加工方法です。
部品同士を結合するためのボルトを通す穴や、ねじを立てるための下穴など、その用途は多岐にわたります。
単純な穴を開けるだけでなく、開けた穴の精度を高めるためにリーマを通したり、穴の径をさらに広げる中ぐり加工を行ったりすることもあります。
ボール盤やマシニングセンタ、旋盤など、多くの工作機械でこの加工が可能です。
切削加工で使われる代表的な工作機械と工具
切削加工によって高精度な部品を生み出すためには、加工の目的に合った工作機械と、材料に適した切削工具の選定が不可欠です。
現代の工作機械はコンピュータによる数値制御(NC)が主流となっており、複雑な加工を自動で行うことができます。
また、加工を直接担う切削工具も、形状や材質が多岐にわたり、これらを適切に使い分けることが品質を左右します。
複合的な加工を自動で行うマシニングセンタ
マシニングセンタは、NC(数値制御)装置を備えた代表的な工作機械です。
フライス加工、穴あけ、ねじ立てといった複数の異なる切削加工を、プログラムに基づいて自動で連続的に行う能力を持っています。
最大の特徴はATC(オート・ツール・チェンジャー)と呼ばれる自動工具交換装置を搭載している点で、これにより人の手を介さずに様々な種類の工具を交換し、一度の段取りで複雑な形状を完成させることが可能です。
この自動化機能により、マシニングは生産性の向上に大きく貢献しています。
複雑な形状に対応できる5軸加工機
5軸加工機は、従来の上下(Z軸)、前後(Y軸)、左右(X軸)の3軸の動きに、回転軸と傾斜軸の2軸を加えた工作機械です。
これにより、工具を様々な角度から材料に当てることが可能となり、一度の段取りで複雑な曲面や傾斜面を持つ部品を効率的に加工できます。
例えば、航空機の部品や人工関節、タービンのブレードといった、滑らかな三次元形状が求められる製品の製造で活躍します。
段取り替えの回数が減るため、加工時間の短縮と精度の向上にもつながります。
加工に欠かせない切削工具の種類
切削工具は、実際に材料を削る役割を担う重要な要素であり、その種類は非常に多岐にわたります。
フライス加工で平面や溝を削る際にはエンドミルが、旋盤加工で丸棒を削る際にはバイトが用いられます。
バイトとは旋盤で使われる刃物の総称です。
これらの工具の先端には、超硬合金やセラミックスといった硬い材質で作られた刃が付いています。
また、刃先が摩耗した際に、刃の部分だけを交換できるインサート(スローアウェイチップ)も広く普及しており、コスト削減と作業効率の向上に貢献しています。
加工内容や材料に合わせて、最適な形状や材質の歯を持つ工具を選ぶ必要があります。
切削加工の精度を高めるために知っておくべき注意点
切削加工で設計通りの高精度な部品を製作するためには、加工プログラムを設定するだけでなく、加工中に発生する様々な物理現象を理解し、対策を講じる必要があります。
特に、機械や工具の剛性、加工によって生じる熱、そして材料を削る際に発生する抵抗力は、最終的な仕上がり品質に大きな影響を及ぼします。
これらの要因を適切に管理することが、安定した高精度加工の鍵となります。
工具や機械の剛性が加工精度に与える影響
切削加工中、工具と材料の間には大きな力や摩擦が発生します。
この力によって工作機械や工具がたわんだり、振動したりすることがあり、これが加工精度を悪化させる一因となります。
特に、工具の突き出し量が長かったり、細い工具で加工したりする場合に「びびり振動」と呼ばれる現象が発生しやすく、加工面に模様がついたり寸法が不安定になったりします。
これを防ぐためには、機械本体の剛性はもちろん、工具や治具も含めたシステム全体の剛性を確保することが求められます。
加工時に発生する熱による寸法変化(熱変形)
切削加工では、工具と材料の摩擦などによって高い熱が発生します。
この熱は、加工している材料や工作機械本体、工具を膨張させ、寸法誤差を引き起こす原因となります。
これを熱変形と呼び、精密な加工を行う上での大きな課題です。
対策として、切削油(クーラント)をかけて冷却と潤滑を行うことが一般的です。
切削油には油性のものと水に薄めて使う水溶性のものがあります。
特に高い精度が要求される場合には、工場の室温を一定に保ったり、加工前に機械を暖機運転させたりして、熱による変形を最小限に抑える工夫が必要です。
切削抵抗が仕上がりの良し悪しを左右する
切削抵抗とは、工具で材料を削り取る際に発生する抵抗力のことです。
この抵抗の大きさは、加工面の粗さや寸法精度、工具の寿命に直接影響を与えます。
切削抵抗が大きすぎると、工具の摩耗が激しくなったり、びびり振動が発生して仕上げ面が悪化したりします。
適切な切削抵抗を保つためには、工具の回転速度や、工具が1回転あたりに進む距離(送り)、一度に削り取る深さ(切り込み量)といった加工条件を最適化することが不可欠です。
送りとは何かといった基本的な条件の理解が、品質管理の第一歩となります。
まとめ
本記事では、切削加工の基礎知識について解説しました。
切削加工は、工具を用いて材料を削り、目的の形状を作り出す除去加工の一種です。
高精度な加工が可能で、多種多様な材料に対応できる一方、加工時間や形状に制約があるという特徴を持ちます。
旋盤加工やフライス加工といった代表的な種類があり、マシニングセンタなどの工作機械が用いられます。
高精度な加工を実現するには、剛性や熱、切削抵抗といった要因への理解が欠かせません。
部品の調達を検討する際は、ミスミ(MISUMI)が提供するようなオンライン機械部品調達サービスを活用するのも一つの方法です。
加工品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら