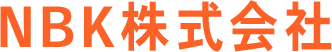アルミとは?
アルミは、私たちの生活のあらゆる場面で使われている非常に身近な金属です。
正式名称をアルミニウムと言い、その軽さや加工のしやすさ、錆びにくさといった優れた特性から、日用品から航空宇宙産業まで、幅広い分野で活用されています。
この記事では、アルミが持つ基本的な性質やメリット・デメリット、他の金属との違いについて網羅的に解説し、この便利な素材への理解を深めていきます。
アルミ(アルミニウム)とはどんな金属?
アルミ(アルミニウム)は、元素記号「Al」、原子番号13の金属元素です。
ボーキサイトという赤褐色の鉱石を精製して作られる「アルミナ」を電気分解することで製造されます。
地球の地殻を構成する元素の中で、酸素、ケイ素に次いで3番目に多く存在する、非常に豊富な資源です。
一般的によく知られているのは1円玉の素材ですが、その他にもアルミサッシやアルミ缶など、様々な製品に利用されている非常にポピュラーな素材です。
アルミが持つ10の優れた特性
アルミは多くの優れた特性を併せ持つ、非常に利用価値の高い金属です。
最大のメリットである軽さに加え、耐食性、加工性、熱伝導性、電気伝導性など、その利点は多岐にわたります。
さらに、合金にすることで強度を大幅に向上させることも可能です。
これらの特性は、製品の軽量化や長寿命化、エネルギー効率の向上に貢献し、様々な産業分野でアルミが採用される理由となっています。
ここでは、アルミが持つ10の代表的な利点について詳しく見ていきます。
アルミ加工品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
鉄や銅の約1/3という軽さ
アルミの最も大きな特徴は、その軽さにあります。
比重が2.7g/cm³であり、これは鉄(7.8g/cm³)や銅(8.9g/cm³)の約1/3に相当します。
この軽量性は、輸送機器の分野で特に重宝されており、例えば車のボディや部品にアルミを使用することで車体重量を大幅に削減できます。
車が軽くなると、燃費の向上や走行性能の改善につながるため、環境負荷の低減にも貢献します。
航空機や新幹線の車両、建築材料など、軽量化が求められるあらゆる場面でアルミのこの特性が活かされています。
高い耐食性でサビの発生を防ぐ
アルミは非常に錆びにくい金属です。
これは、アルミが空気中の酸素と反応すると、表面に「酸化皮膜」と呼ばれる非常に薄く、緻密で安定した膜を自然に形成するためです。
この酸化皮膜がバリアとなり、内部の金属を腐食から保護します。
万が一、表面に傷がついて皮膜が剥がれても、瞬時に再生する自己修復機能も持っています。
鉄の赤サビのようにボロボロと剥がれ落ちることがないため、長期間にわたって美観を保つことが可能です。
この特性を活かし、屋外で使用される建材のアルミサッシやガードレール、台所用品などに広く利用されています。
合金にすると高い強度を発揮する
純粋な状態のアルミは柔らかく、強度が低い金属です。
しかし、銅やマグネシウム、亜鉛、ケイ素といった他の元素を添加して合金にすることで、その強度を飛躍的に向上させることが可能です。
このアルミ合金は、添加する元素の種類や量によって特性が異なり、JIS規格によって1000番台から7000番台まで分類されています。
特に亜鉛とマグネシウムを主成分とする7000番台のアルミ合金は、鋼材に匹敵するほどの高い強度を誇り、航空機の翼や構造部品など、軽さと強度が同時に求められる過酷な環境で使用されています。
低温環境でも強度を維持できる
多くの鉄鋼材料は、温度が低くなるにつれて脆くなる「低温脆性」という性質を示します。
しかし、アルミは極低温環境下でもこの脆性破壊を起こさず、むしろ温度の低下とともに強度や延性が向上するという優れた特性を持っています。
例えば、-196℃の液体窒素の中でも、その強度は常温時に比べて高くなります。
この性質により、液化天然ガス(LNG)を貯蔵するタンクや輸送船、宇宙ロケットの燃料タンクなど、超低温が要求される分野で不可欠な材料として活躍しています。
引張強さや0.2%耐力といった指標も低温下で向上する傾向があります。
様々な形状に加工できる優れた加工性
アルミは柔らかく延性に富むため、様々な形状に加工しやすいという利点があります。
圧力をかけて薄く延ばす「圧延」、金型を通してところてんのように押し出す「押出」、溶かして型に流し込む「鋳造」、刃物で削る「切削」など、多彩な加工方法に対応できます。
非常に薄く延ばすことも可能で、家庭で使われるアルミホイルはその代表例です。
この優れた加工性により、複雑な形状の部品や建材、飲料缶などを簡単に、かつ高精度で大量生産することができます。
設計の自由度が高まるため、デザイン性が求められる製品にも適しています。
熱伝導率が高く熱を伝えやすい
アルミは熱を非常に伝えやすい性質を持っています。
その熱伝導率は鉄の約3倍にも達し、金属の中でも銅に次いで高いレベルです。
この特性を活かし、熱を素早く均一に伝えることが求められる調理器具、例えば鍋やフライパン、やかんなどに広く利用されています。
熱が一部に集中することなく全体に広がるため、調理時の焼きムラを防ぐ効果があります。
また、熱を効率的に逃がす(放熱する)能力も高いため、パソコンのCPUや電子機器、LED照明などの熱に弱い部品を冷却するためのヒートシンク(放熱板)の材料としても不可欠な存在です。
電気をよく通す高い導電性
アルミは電気をよく通す性質、すなわち高い導電性を持っています。
その導電率は銅の約60%程度ですが、比重が銅の約1/3と非常に軽いため、同じ重さで比較すると銅の約2倍の電気を通すことが可能です。
この「重量あたりの導電率」の高さがアルミの大きな利点であり、高電圧を送るための送電線やケーブルに広く採用されています。
送電線を支える鉄塔の負担を軽減できるほか、コスト面でも銅より安価であるため、電力インフラにおいて重要な役割を担っています。
0.5mmといった細い電線にも加工できる柔軟性も持ち合わせています。
磁石につかない非磁性体である
アルミは磁石に引きつけられない「非磁性体」という性質を持っています。
磁場の中に置いても磁化されることがなく、磁力の影響を受けません。
この特性は、磁気が性能に影響を与える精密機器や電子機器にとって非常に重要です。
例えば、ハードディスクの基板やパラボラアンテナ、医療現場で使用されるMRI(磁気共鳴画像装置)の周辺機器など、磁気を嫌う環境で広く活用されています。
また、強力な磁場を発生させるリニアモーターカーの車体にも、この非磁性という特性を活かしてアルミが使われています。
4CGS単位系における磁化率は非常に小さい値を示します。
光や熱を効率よく反射する
アルミは銀白色の美しい見た目を持ち、光や熱、電磁波をよく反射する特性があります。
特に赤外線や紫外線の反射率が高く、研磨などの表面処理を施すことで、その反射率をさらに90%以上に高めることも可能です。
この性質を利用して、照明器具のリフレクター(反射板)や暖房器具の反射板、魔法瓶の内側などに使われ、エネルギー効率を高める役割を担っています。
また、素地のままでも美しい光沢を持つため、装飾品や建材のパネルなど、デザイン性が求められる用途にも適しています。
この見た目の良さもアルミの魅力の一つです。
環境に優しいリサイクル可能な金属
アルミは「リサイクルの優等生」と呼ばれるほど、リサイクルに適した金属です。
品質をほとんど劣化させることなく、何度でも再生して利用することができます。
さらに、リサイクルに必要なエネルギーは、原料のボーキサイトから新しく地金を作る場合に比べて、わずか3%程度で済みます。
これにより、エネルギー消費量とCO2排出量を大幅に削減でき、環境負荷の低減に大きく貢献します。
アルミ缶や自動車部品、建築廃材のサッシや家の屋根材など、使用済みのアルミ製品は効率的に回収・再生され、新たな製品へと生まれ変わっています。
アルミ部品でお困りの図面がありましたらNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら
アルミ合金とは?純アルミニウムとの違いを解説
一般的に「アルミ」として流通している製品の多くは、純粋なアルミニウムではなく、他の金属を添加した「アルミ合金」です。
純アルミニウムは柔らかく加工しやすい反面、強度が低いという欠点があります。
そこで、強度や耐食性、切削性といった特定の性能を向上させる目的で、銅、マンガン、ケイ素、マグネシウム、亜鉛などを加えたものがアルミ合金です。
アルミの優れた特性を活かしつつ、用途に応じて弱点を補強できるのがアルミ合金の大きな特徴であり、純アルミとの最大の違いと言えます。
加工して使う「展伸用合金」
展伸用合金とは、圧延、押出、鍛造といった塑性加工によって板や棒、管、形材などに成形されるアルミ合金の総称です。
JIS規格では添加されている主要な元素によって1000番台から7000番台まで分類されています。
例えば、マグネシウムを添加した5000番台は耐食性や溶接性に優れ、船舶や車両部品に用いられます。
マグネシウムとケイ素を添加した6000番台は強度、耐食性、加工性のバランスが良く、建築用サッシや機械構造材、ねじ類に広く使われます。
このように、用途に応じて最適な特性を持つ合金が選ばれています。
鋳造して使う「鋳物用合金」
鋳物用合金とは、溶かしたアルミを砂や金属で作られた鋳型に流し込んで製品を作る「鋳造」に適したアルミ合金です。
複雑な形状の製品を一体で製造できるのが特徴で、自動車のエンジン部品やシリンダーブロック、ホイールなどに多用されます。
鋳物用合金には、溶けた金属の流動性(湯流れ)を良くし、鋳造時の割れを防ぐために、ケイ素(Si)が多く添加されています。
展伸用合金に比べて強度では劣る場合もありますが、寸法精度が高く、複雑な形状のものを効率的に量産できるという大きな利点を持っています。
アルミを使用する際に知っておきたい注意点
アルミは多くの優れた特性を持つ一方で、使用する際にはいくつかの注意点や欠点も理解しておく必要があります。
万能な材料というわけではなく、鉄鋼材料と比較して強度が劣る点や、特定の環境下では腐食が進む可能性、さらには加工の難易度が高い側面も持ち合わせています。
これらのデメリットを把握し、設計や使用環境を考慮することで、アルミの性能を最大限に引き出すことができます。
ここでは、アルミを利用する上で知っておくべき代表的な注意点を解説します。
鉄などの金属に比べて強度が劣る場合がある
アルミは合金にすることで強度を高められますが、一般的な鉄鋼材料と比較すると、絶対的な強度や剛性(変形のしにくさ)の面では劣る場合があります。
特に、物体の変形しにくさを示すヤング率は鉄の約1/3しかなく、同じ形状であれば鉄よりもたわみやすい性質を持ちます。
このため、橋梁や高層ビルなど、非常に高い強度が求められる主要な構造部材には鉄が使われることが多くなります。
アルミを構造材として使用する際は、強度不足を補うために板厚を増したり、断面形状を工夫したりする設計上の配慮が必要になってきます。
実際に強度を試してみると、その差を体感できるでしょう。
特定の環境下では腐食することがある
アルミは通常、表面の酸化皮膜によって高い耐食性を発揮しますが、この皮膜が化学的に破壊される環境では腐食することがあります。
特に、強アルカリ性や強酸性の溶液には弱く、表面の皮膜が溶解してしまいます。
また、海水や潮風に含まれる塩素イオンも皮膜を部分的に破壊し、孔食(点状の深い腐食)を引き起こす原因となります。
さらに、銅や鉄など、アルミより電位の高い異種金属と接触した状態で水分が付着すると、電池が形成されてアルミ側の腐食が急速に進行する「異種金属接触腐食」にも注意が必要です。
溶接加工の難易度が高い
アルミは鉄鋼材料に比べて溶接の難易度が高い金属です。
その理由の一つに、表面を覆う酸化皮膜の存在が挙げられます。
アルミ自体の融点が約660℃と低い一方、酸化皮膜の融点は約2000℃と非常に高いため、溶接時にこの皮膜が溶融を妨げ、溶接欠陥の原因となります。
また、熱伝導率が高すぎて溶接部の熱が急速に拡散し、歪みや溶け込み不良が生じやすいという問題もあります。
TIG溶接やMIG溶接といった特殊な溶接方法や、ろう付けなどの技術が必要となり、鉄の溶接に比べて高いスキルと適切な設備が求められます。
他の金属(鉄・ステンレスなど)とアルミの性質を比較
材料を選定する際には、他の金属との比較を通じてそれぞれの特性を理解することが重要です。
アルミと代表的な金属材料である鉄、ステンレス、銅を比較すると、その違いが明確になります。
例えば、軽さ(比重)ではアルミが圧倒的に優位ですが、強度や硬度では鉄やステンレスに軍配が上がります。
耐食性ではステンレスとアルミが高いレベルにあり、熱や電気の伝導性では銅やアルミが優れています。
このように、アルミと他の金属は一長一短の関係にあり、コストも含めて総合的に判断し、用途に最適な材料を選ぶ必要があります。
まとめ
アルミは、軽量、高耐食、良加工性、高熱伝導性、リサイクル性の高さといった数多くの優れた特性を併せ持つ、非常に有用な金属材料です。
その用途は日用品から産業機器、輸送機器、建築材料まで多岐にわたります。
一方で、鉄鋼材料に比べた場合の強度不足や特定の環境下での腐食、溶接の難しさといった側面も存在します。
アルミやその他の金属には、それぞれに適した用途と不得意な分野があります。
まるで歯の治療で材料を選ぶように、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、目的に応じて最適な材料を選定することが重要です。
アルミ加工品のコストダウンや納期短縮、品質向上のご相談はNBKにお任せください!
お問い合わせはこちら
資料ダウンロードはこちら